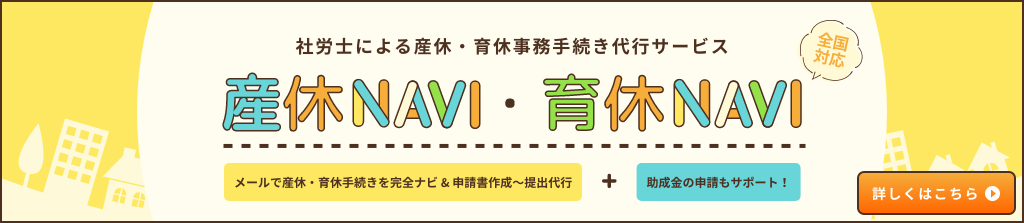■
この記事では「くるみん」認定について、「トライくるみん」「プラチナくるみん」認定も含め、その概要と取得メリット、申請手順および認定条件について分かりやすく解説しています。
くるみん認定とは?
くるみん認定とは、厚生労働大臣による認定制度で、各企業が「仕事と子育ての両立等、次世代育成のための支援」を自発的に行うよう促す目的で設けられました。
あらかじめ、所定の基準を上回る目標を定めた行動計画(次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」)を策定し、その計画目標全てをクリアした事業主が申請できます。
くるみん認定の種類
くるみん認定には、通常の「くるみん認定」以外にも、以下の認定基準があります。
なお、はじめての事業主は「くるみん認定」「トライくるみん認定」のいずれかについてのみ取得をめざすことができます。
■くるみん認定
標準となる認定基準を満たした場合に取得することができる認定です。
■トライくるみん認定
「くるみん認定」よりも少し低い認定基準〔直近(令和7年4月1日)基準改定前の旧くるみん認定基準〕をクリアした場合に申請できます。
■プラチナくるみん認定
「くるみん認定」「トライくるみん」認定を受けた事業主がより高い水準の取組を行い、一定の基準を満たした場合は、さらに「プラチナくるみん認定」を受けることができます。
すでに「くるみん認定」または「トライくるみん認定」を取得している事業主でなければ申請できません。
■プラス認定
上記の各認定に加えて、一定の不妊治療サポート基準を満たした場合は、さらに「プラス認定」を追加で取得することができます。
「くるみん」「トライくるみん」「プラチナくるみん」の各認定事業主が「プラス認定」を追加取得した場合は「くるみんプラス」「トライくるみんプラス」「プラチナくるみんプラス」の各認定を取得することができます。
◇この記事では、「プラス認定」の認定基準は説明しておりません。詳細は(厚生労働省:令和7年3月作成パンフレット)をご参照下さい。
くるみん認定取得のメリット
メリット1:認定マーク使用によるPR効果
各認定を受けた事業主は、それぞれの認定内容に応じて、厚生労働大臣が定めた「認定マーク」を商品・広告・求人広告などに表示して、子育てサポート企業であることをPRすることができます。
なお、令和7年4月1日より、各認定の基準が従前より厳格化されています。
この関係で、令和7年4月1日以降の新基準により認定を受けた事業主は、従前とは異なる認定マークを使用できることとなっています。
ちなみに、令和9年3月31日までの間に認定申請を行う場合は、令和7年3月31日までの旧基準に基づき申請することも可能です。
(旧基準で認定を受けた場合は、旧基準の認定マークが付与されます。)
また「プラス」認定を取得すれば、不妊治療と仕事との両立サポート企業であることも追加でPRすることができます。
令和7年4月1日以降の「認定マーク」は以下の通りとなります。(厚生労働省:令和7年3月作成パンフレットより引用)
【くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん】

【くるみんプラス・トライくるみんプラス】

【プラチナくるみんプラス】

メリット2:公共事業の調達における加点評価
「くるみん」「トライくるみん」「プラチナくるみん」の各認定(*)を受けた企業には、各府省による公共調達において加点評価等が行われますので、落札や競争調達による受注案件への参加を有利に進めることができます。
上記の加点評価は地方公共団体に対しても、公共調達を行う際、国に準じた取組を行うよう努力義務が課されています。
*「プラス認定」を受けても優遇内容は拡充されません。
メリット3:賃上げ促進税制の優遇
「くるみん」「くるみんプラス」「プラチナくるみん」「プラチナくるみんプラス」の各認定を取得した企業は、「賃上げ促進税制」において、税額控除率の優遇措置を受けることができます。
メリット4:両立支援等助成金の加算措置
「プラチナくるみん」認定を受けた企業は、育休関連の両立支援等助成金を申請する際、加算措置を受けられる場合があります。
メリット5:日本政策金融公庫「働き方改革推進支援資金」貸付の金利優遇
次世代育成支援対策推進法による「一般事業主行動計画」の策定義務がない、常時雇用者数100人以下の事業主が、「くるみん」「プラチナくるみん」の各認定を取得した場合は、日本政策金融公庫の貸付制度である「働き方改革推進支援資金」を利用する際、金利の優遇を受けられる場合があります。
それでは引き続き、くるみん認定を取得するための手順について見ていきましょう。
当事務所では、くるみん認定、プラチナくるみん認定の取得を円滑に進められるよう・・・
①次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の作成・届出・公表手続代行サービス
②くるみん認定、プラチナくるみん認定申請手続き代行サービス
を顧問契約不要・安心の一括スポット料金でご提供しております。
(①と②のサービスは別々でのご提供となります)
完全オンライン対応でサポート致します。
- ご多忙につき、「情報収集の時間確保」が難しいご担当者様
- 業務中断せず、自分のペースで支援を受けたいご担当者様
から大変ご好評いただいております。
【全国47都道府県対応】
メールで気軽に支援が受けられる!
CLASSY. 2024年2月号に掲載されました。
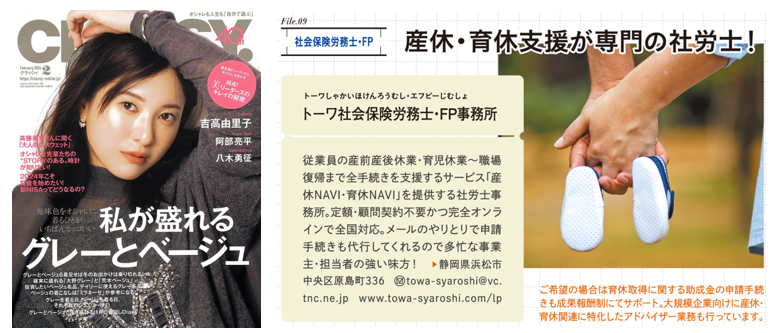
企業実務2025年2月号に寄稿しました。
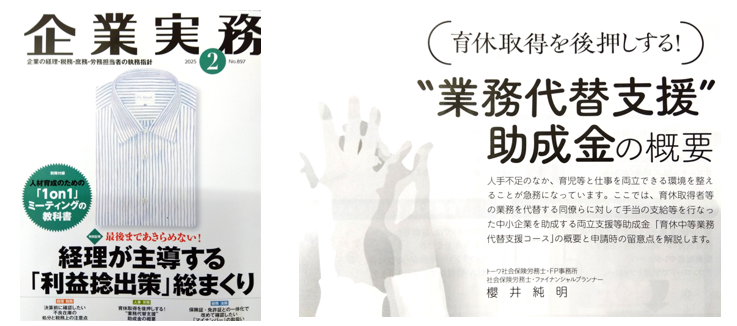
2025年4月「@Living」の取材に協力しました。

【両立支援等助成金・東京都奨励金 活用のご案内】
従業員の育休取得を推進する中小企業に対しては、非常に手厚い助成金・奨励金制度が設けられています!
育休関連の助成金・奨励金制度について知りたい方は、以下のサイトもご参照下さい。
欠員補充コストでお悩みの事業主様には、是非とも知っておいていただきたい内容となっています。
産休・育休関連情報 総合ページへのリンクはこちら!
以下のページからアクセスすれば、産休・育休関連の【各種制度・手続き情報】【最新の法改正情報】から【助成金関連情報】まで、当サイトにある全ての記事内容を閲覧することができます。
くるみん認定を取得するための手順
くるみん認定を取得するためには、以下①~⑥全ての手順を経たうえで、厚生労働大臣による認定を受けなければなりません。
①認定基準として定められた複数の基準全てを満たす「一般事業主行動計画(2年以上5年以下の範囲内で定めたもの)」を策定
↓
②策定した行動計画を社内周知
↓
③社内周知済の計画を厚生労働省サイト(両立支援のひろば)へ公開
↓
④行動計画策定届を所轄の都道府県労働局へ提出
↓
⑤行動計画を計画期間内に実施
↓
⑥所轄都道府県労働局へ認定申請(全ての計画目標クリアが認定条件)
くるみん(トライくるみん・プラチナくるみん)の認定基準
令和7年4月1日以降は、次世代育成支援対策推進法の改正により「くるみん」「トライくるみん」「プラチナくるみん」ともに認定基準が厳格化されています。
なお、法改正のある箇所については、以下の各説明書き下段に旧基準からの変更点を補記してあります。
◇この記事では、「プラス認定」の認定基準は説明しておりません。詳細は(厚生労働省:令和7年3月作成パンフレット)をご参照下さい。
認定基準1:適切な行動計画を策定していること
まずは「行動計画策定指針」に則り、適切な「一般事業主行動計画」を策定しなければなりません。
具体的には「一般事業主行動計画」を策定する際、以下「行動計画策定指針」の「六 一般事業主行動計画の内容に関する事項」に定められている「1 雇用環境の整備に関する事項(1)(2)」に示された項目(後述ご参考)の中から、1項目以上を盛り込まなければなりません。
【六 一般事業主行動計画の内容に関する事項】
以下の記載は「行動計画策定指針」より抜粋した項目を読みやすく簡略化し、箇条書きにしてあります。
実際に「一般事業主行動計画」を策定する際には、「行動計画策定指針」本文、または「厚生労働省パンフレット」を必ずご確認下さい。
1 雇用環境の整備に関する事項
(1) 妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援するための雇用環境の整備
ア 妊娠中及び出産後における配慮
・母性保護及び母性健康管理についての制度周知、情報提供、相談体制整備など
イ 男性の子育て目的の休暇の取得促進
・子育てを目的とした企業独自の休暇
・産後8週間以内の期間における育児休業
・小学校就学後の子育てのための休暇
の取得促進など
ウ より利用しやすい育児休業制度の実施
・育児介護休業法を上回る措置の実施など
エ 育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備
・出生時育児休業及び「パパ・ママ育休プラス」の制度等についての周知
・育休規定の整備、社内周知
・育児休業期間中の代替要員確保、業務内容や業務体制の見直し
・育児休業をしている労働者の職業能力開発及び向上等
・育児休業後における原職又は原職相当職への復帰
など
オ 子育てをしつつ活躍する女性労働者を増やすための環境の整備
・出産、子育てを経験し働き続けるキャリアイメージ形成支援の為の研修
・社内ロールモデルと女性労働者のマッチング及びメンター制度
・復職後又は子育て中の女性労働者を対象とした能力向上のための取組
・キャリア形成を支援するためのカウンセリング
・男性労働者が従事してきた職務への女性労働者の積極配置
・女性労働者に対する職域拡大に向けた管理職研修
・管理職手前の女性労働者に対するマネジメント研修
・企業トップ等による女性の活躍推進風土の改革に関する研修
・昇進基準及び人事評価制度の見直し
の実施など
カ 短時間勤務制度等の実施
3歳以上の子どもを養育する労働者に対する
・短時間勤務制度
・フレックスタイム制度
・始業・終業時刻の繰上げ又は繰下げの制度
の実施など
キ 事業所内保育施設の設置及び運営
ク 子育てサービス費用援助措置の実施
ケ 子どもの看護のための休暇措置の実施
・始業の時刻から連続せず、終業の時刻まで連続しない時間単位での取得を認める
措置など
コ 職務や勤務地等の限定制度の実施
サ その他子育てを行う労働者に配慮した措置の実施
・子育てを行う労働者の社宅への入居に関する配慮
・子育て費用の貸付け・学校行事参加のための休暇制度
の実施など
シ 不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施
・不妊治療のために利用することができる休暇制度
・所定外労働の制限
・始業終業時刻の繰上げ又は繰下げの制度
・フレックスタイム制
・短時間勤務制度
・テレワーク
・不妊治療と仕事の両立推進に関する企業方針周知、相談対応
の実施など
ス 諸制度の周知
・育児介護休業法に基づく労働者の権利や、休業期間中の育児休業給付の支給等諸制度について周知
セ 育児等退職者についての再雇用特別措置等の実施
(2) 働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備
ア 時間外・休日労働の削減
・労働時間等設定改善委員会等、労使間の話合いの機会の整備
・ノー残業デーやノー残業ウィークの導入・拡充
・フレックスタイム制や変形労働時間制の活用
・時間外労働協定における延長時間の短縮
など
イ 年次有給休暇の取得の促進
ウ 短時間正社員等の多様な正社員制度の導入・定着
エ テレワーク等の導入
オ 職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組
なお、令和7年4月1日以降、「一般事業主行動計画」を策定・変更する際には、以下の「数値目標」設定を計画に織り込むことが、新たに義務付けられていますのでご注意下さい。
【令和7年4月1日以降、設定が義務付けられた内容】
「一般事業主行動計画」を策定・変更する際・・・
・男性労働者の「育児休業等取得率」又は「育児休業等及び育児目的休暇の取得率」
・フルタイム労働者1人あたり各月ごとの「法定時間外労働」及び「法定休日労働」の合計時間数
を把握した上で、計画期間中に達成すべき・・・
①男性労働者の「育児休業等取得率」又は「育児休業等及び育児目的休暇の取得率」
②フルタイム労働者1人あたりの月平均「法定時間外労働」+「法定休日労働時間数」(*)
(*)高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者については「健康管理時間」
を数値目標として設定することが義務化されています。
認定基準2:2年以上5年以下の計画を策定していること
「一般事業主行動計画」は、2年以上5年以下の範囲内で策定されていなければなりません。
認定基準3:策定した行動計画の目標を達成していること
策定した「一般事業主行動計画」は、計画期間内に実施され、その全ての設定目標が達成されていなければなりません。
なお、目標の達成を証明するため、以下のようなエビデンス提出が必要となります。
【目標達成エビデンスの例】
・制度導入後の就業規則(写)
・制度導入時に社内周知した書面(制度導入年月日が分かるもの)
・育休取得者の氏名・休業期間等が記載された書面
・行動計画に定められた労働者1人あたりの各月所定外労働時間数等を明記したもの
等、証明すべき内容に応じてその確認ができるエビデンス
認定基準4:行動計画の公表と社内周知が行われていること
策定・変更した「一般事業主行動計画」については、厚生労働省サイト「両立支援のひろば」を通じて公表され、従業員に対しても適切に社内周知されていなければなりません。(計画策定後おおむね3か月以内に周知が必要です)
認定基準5:所定の男性育休等取得率を達成していること
計画期間内に生じたものをすべて通算し、以下 a)あるいは b)のいずれかを達成し、その実績数値を、厚生労働省サイト「両立支援のひろば」に公表済でなければなりません。
なお、以下に示す「育児休業等」とは育児・介護休業法に規定する「育児休業(出生時育児休業を含む)」「3歳未満の子を育てる労働者を対象とした育児休業」「小学校就学前の子を育てる労働者を対象とした育児休業」のことを指します。
a)
「男性育児休業等取得率」30%〔トライ10%・プラチナ50%〕以上
令和7年4月1日より基準引上げ
(旧基準:男性育児休業等取得率10%〔トライ7%・プラチナ30%〕以上)
b)
「男性育児休業等取得率」あるいは「会社独自の育児目的休暇 利用率」が50%(トライ20%・プラチナ70%)以上、かつ、男性育児休業等取得者数が1人以上
令和7年4月1日より基準引上げ
(旧基準:「男性育児休業等取得率」あるいは「会社独自の育児目的休暇 利用率」が20%〔トライ15%・プラチナ50%〕以上、かつ、男
性育児休業等取得者数1人以上)
なお、常時雇用労働者数が300人以下の事業主に対しては、以下のとおり別途、例外基準が定められています。
<常時雇用労働者数300人以下の事業主の例外基準>
常時雇用労働者数300人以下の事業主については、男性の育児休業等取得者または会社独自の育児目的休暇を利用した男性労働者がいない場合のみ、以下①~④いずれかの基準を満たしていれば、上記 a) および b) の基準を満たしていなくても認定対象となります。
①計画期間内に、1歳以上小学校就学前までの子を対象として「子の看護等休暇制度」を利用した男性労働者がいること
②計画期間内に、中学校卒業前の子を対象とした「所定労働時間の短縮措置」を利用した男性労働者がいること
③計画期間内の全てとその開始前の一定期間〔最長3年間〕をあわせて計算したときに、男性の育児休業等取得率が30%〔トライ10%・プ ラチナ50%〕以上あること*
④計画期間内に小学校就学前の子を養育する男性労働者がいなかった場合は、中学校卒業前の子、または小学校就学前の孫について、会社独自の育児目的休暇制度を利用した男性労働者がいること
*令和7年4月1日より基準引上げ
(旧基準:③計画期間内の全てとその開始前の一定期間〔最長3年間〕をあわせて計算したときに、男性の育児休業等取得率が10%
〔トライ7%・プラチナ30%〕以上あること)
なお、上記①~④いずれの場合も、当該実績数値を厚生労働省サイト「両立支援のひろば」に公表済でなければなりません。
認定基準6:所定の女性育休等取得率を達成していること
計画期間内に生じたものをすべて通算し、以下 a)b)を両方とも達成し、その実績数値を、厚生労働省サイト「両立支援のひろば」に公表済でなければなりません。
なお、以下に示す「育児休業等」とは育児・介護休業法に規定する「育児休業」「3歳未満の子を育てる労働者を対象とした育児休業」「小学校就学前の子を育てる労働者を対象とした育児休業」のことを指します。
a)
女性労働者の育児休業等取得率75%以上
b)
育児休業等の取得対象となる女性有期雇用労働者の育児休業等取得率75%以上*
*令和7年4月1日より基準引上げ(旧基準は上記 a)の基準のみであったところ b) の基準が新たに追加されています)
こちらについても、常時雇用労働者数が300人以下の事業主に対し、別途、例外基準が定められています。
<常時雇用労働者数300人以下の事業主の例外基準>
常時雇用労働者数300人以下の事業主については、計画期間内の女性の育児休業等取得率が75%に満たなくても・・・
・計画期間とその開始前の一定期間(合計して最長3年間まで)を合算して、女性の育児休業等取得率が75%以上
あるいは
・育児休業等の取得対象となる女性有期雇用労働者の育児休業等取得率が75%以上
のいずれか*
を満たせば、厚生労働省サイト「両立支援のひろば」に実績数値を公表済であることを前提に認定対象となります。
*令和7年4月1日から基準追加(旧基準:上記の定めにおいて「あるいは育児休業等の取得対象となる女性有期雇用労働者の育児休業等取得率が
75%以上のいずれか」の部分がなく、新たに追加されています)
認定基準7:時間外労働の各月平均時間数が所定の範囲内におさまっていること
計画期間終了日の属する事業年度(企業会計の決算年度)各月の法定時間外労働において・・・
以下 a) および b) の両方を満たしていなければなりません。
a)
全てのフルタイム労働者の「法定時間外労働+法定休日労働」の1人あたり平均時間数が、各月毎に30時間(トライ45時間)以上となる月がないこと*
あるいは
25歳~39歳のフルタイム労働者の「法定時間外労働+法定休日労働」の1人あたり平均時間数が、各月毎に45時間以上となる月がないこと(トライにこの基準は適用されません)
*令和7年4月1日より基準引上げ
(旧基準:全てのフルタイム労働者の「法定時間外労働+法定休日労働の1人あたり平均時間数が、各月毎に45時間以上となる月がないこと
のみ〔25歳~39歳を対象とした基準はなし〕)
b)
法定時間外労働が各月を平均して1か月あたり60時間以上となる労働者がいないこと
認定基準8:所定の雇用環境整備措置を実施していること
以下 a~c いずれかの措置について定め、「一般事業主行動計画」の計画期間が終了するまでに実施していなければなりません。
なお、プラチナくるみん認定を申請する場合は、以下 a~c 全ての措置を実施し、うち a.b. のいずれか一方については、さらに具体的な数値目標を定め、達成までしていることが必要となります)
a.男性労働者の育児休業等の取得期間延伸*のための措置
b.年次有給休暇取得促進のための措置
c.その他働き方の見直しに資する多様な労働条件整備のための措置
*令和7年4月1日より基準変更
上記a.の措置は、もともと「所定外労働削減のための措置」とされていましたが、令和7年4月1日以降、「男性労働者の育児休業等の取得期間の延伸」の措置へ差し替えされ、適用されることとなりました。
【具体的な措置内容と目標設定例】
上記 a~c の具体的な措置内容例と、プラチナくるみん認定を申請する場合の目標設定例は以下のとおりとなります。
なお、これらの措置は「一般事業主行動計画」を策定する前から実施されているものでも差し支えありません。
一方、プラチナくるみん認定を申請する場合の目標は「一般事業主行動計画」の計画期間終了1年前までに設定しておく必要があります。
(一般事業主行動計画の中に目標を折り込む必要はありません)
a.男性労働者の育児休業等の取得期間延伸のための措置
・育休等取得者の業務代替者の確保と職場内業務代替者への業務代替手当支給
・定期的な労働者の意識調査と改善策の実施
・職場と家庭の両方において貢献できる職場風土づくりに向けた意識啓発の実施
・長期の育休等取得を可能とするための環境整備(業務棚卸~複数担当制の確立など)
・安心して育休等を取得し、職場復帰できる環境の構築(ハラスメント防止研修の実施)
<プラチナくるみん認定申請時の目標設定例>
・男性の育児休業等の平均取得期間を○日以上とする
b.年次有給休暇取得促進のための措置
・年次有給休暇の計画的付与制度導入
・年間の年次有給休暇取得計画の策定
・年次有給休暇の取得率目標設定やその取得状況を労使間で話し合い確認する制度の導入
<プラチナくるみん認定申請時の目標設定例>
・年次有給休暇取得率を○%以上とする
c.その他働き方の見直しに資する多様な労働条件整備のための措置
・短時間正社員制度の導入
・在宅勤務等の導入
・職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識などの是正のための取組
・子どもの学校行事への参加のための休暇制度(育児・介護休業法に基づく子の看護等休暇を上回る制度に限る)の導入
認定基準9:法令を遵守していること
法および法に基づく命令、その他関係法令に違反する重大な事実があってはなりません。
追加認定基準1〔プラチナのみ〕:所定の女性労働者「在籍率」目標を達成していること
以下の a) または b)のいずれかを満たし、厚生労働省サイト「両立支援のひろば」に公表済であること。(こちらの基準については、常時雇用労働者数が300人以下の事業主に対し、別途、後述のとおり例外基準が定められています。)
a)
子を出産した女性労働者について、子の1歳誕生日まで継続して在籍している者(育休取得中の者を含む)の割合が90%以上あること
b)
子を出産した女性労働者および出産予定の段階で退職した女性労働者の合計数に対して、子の1歳誕生日まで継続して在籍している者(育休取得中の者を含む)の割合が70%以上あること
<常時雇用労働者数300人以下の事業主の例外基準>
常時雇用労働者数300人以下の事業主については、上記 a) あるいは b) いずれの基準も満たさなくても・・・
計画期間とその開始前の一定期間(合計して最長3年間まで)を合算して、a) の割合が90%以上、あるいは b) の割合が70%以上あれば厚生労働省サイト「両立支援のひろば」に公表済であることを前提に認定対象となります。
追加認定基準2〔プラチナのみ〕:育児中労働者への能力向上、またはキャリア形成支援が行われていること
育児休業し、または育児を行う労働者が職業生活と家庭生活との両立を図りながら、その意欲を高め、かつその能力を発揮することで活躍できるような「能力向上またはキャリア形成支援のための取組にかかる計画」を策定し、実施していること
が必要です。
*令和7年4月1日より基準変更
上記基準の文言のうち、「労働者が職業生活と家庭生活との両立を図りながら、その意欲を高め、かつその能力を発揮することで・・・」の部分は、もともと「女性労働者が就業を継続し・・・」の文言となっていたものから差し替えされました。
対象を女性労働者に限定せず、計画策定するよう基準が変更されています。
認定取得後の公表済情報 更新ルール〔プラチナのみ〕
プラチナくるみんの認定を取得した事業主は、認定取得時に「両立支援のひろば」への公表が必要とされている項目について、毎年少なくとも1回、公表日の前事業年度(企業会計の決算年度)の状況について「両立支援のひろば」へ公表済の情報を更新しなければなりません。
なお、更新のタイミングは・・・
・1回目の更新は、プラチナくるみん認定取得後、必要があれば概ね3か月以内
・2回目以降の更新は、各公表前事業年度の終了後、概ね3か月以内
となります。
【プラチナくるみん認定の取り消しについて】
プラチナくるみん認定は、認定取得時に「両立支援のひろば」へ公表が必要とされている項目について、認定後、2年連続で基準を達成できなかった場合は失効し、認定が取消されます。
ただし、公表前事業年度に令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間が含まれている場合は、新基準を満たしていなくても旧基準を満たしていれば取消されることはありません。
令和7年4月1日以降、廃止となった認定基準〔ご参考〕
3歳~小学校就学前の子を養育する労働者に対し・・・
・会社独自の育児休業に関する制度
・所定外労働の制限に関する制度
・所定労働時間の短縮措置、または始業時刻変更等の措置に準ずる制度
を講じることとしていた認定基準は、令和7年4月1日以降、廃止となっております。
認定申請にかかる経過措置
■
令和9年3月31日までの間に認定申請を行う場合は、令和7年3月31日までの旧基準に基づき申請することも可能です。
(旧基準で認定を受けた場合は、旧基準の認定マークが付与されます。)
■
令和7年3月31日以前に開始した行動計画について、令和7年4月1日以降に認定申請を行う際には・・・
・令和7年4月1日以降の計画期間のみを対象として、新基準により認定申請をすること。
・令和7年3月31日以前の計画期間も含め、旧基準により認定申請すること
のいずれの方法でも申請することが可能です
この場合、新基準で認定を受けた場合は新基準のマークが、旧基準で認定を受けた場合は旧基準の認定マークが付与されます。
まとめ
ここまで説明してきました通り、くるみん認定を取得するためには、行動計画の策定から始め、計画目標を達成するまで、数年間を要することとなります。
しかしながら、この認定を取得したあかつきには、子育てサポート企業(および不妊治療と仕事との両立サポート企業)であることを強力にPRすることができ、人材採用を有利に進めやすくなる等、多くのメリットを享受することができます。
貴社もこの際、我が国喫緊の課題である次世代育成支援対策について、一企業として本腰を入れて取り組まれてみてはいかがでしょうか?
なお、この記事では説明できていない「プラス」認定の申請方法等については(厚生労働省:令和7年3月作成パンフレット)をご参照下さい。
当事務所では、くるみん認定、プラチナくるみん認定の取得を円滑に進められるよう・・・
①次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の作成・届出・公表手続代行サービス
②くるみん認定、プラチナくるみん認定申請手続き代行サービス
を顧問契約不要・安心の一括スポット料金でご提供しております。
(①と②のサービスは別々でのご提供となります)
完全オンライン対応でサポート致します。
- ご多忙につき、「情報収集の時間確保」が難しいご担当者様
- 業務中断せず、自分のペースで支援を受けたいご担当者様
から大変ご好評いただいております。
【全国47都道府県対応】
メールで気軽に支援が受けられる!
CLASSY. 2024年2月号に掲載されました。
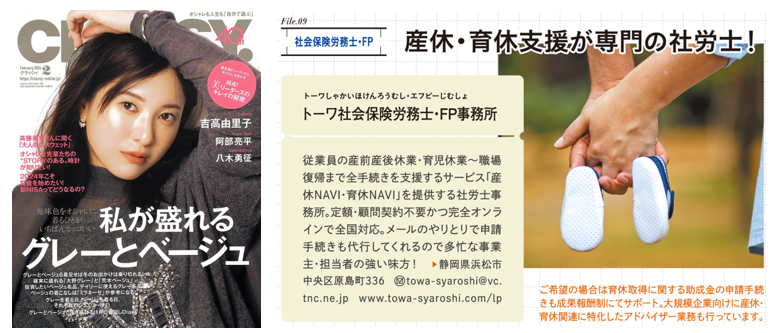
企業実務2025年2月号に寄稿しました。
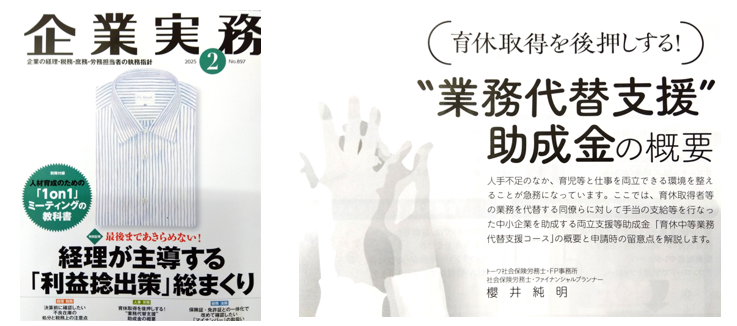
2025年4月「@Living」の取材に協力しました。

【両立支援等助成金・東京都奨励金 活用のご案内】
従業員の育休取得を推進する中小企業に対しては、非常に手厚い助成金・奨励金制度が設けられています!
育休関連の助成金・奨励金制度について知りたい方は、以下のサイトもご参照下さい。
欠員補充コストでお悩みの事業主様には、是非とも知っておいていただきたい内容となっています。
産休・育休関連情報 総合ページへのリンクはこちら!
以下のページからアクセスすれば、産休・育休関連の【各種制度・手続き情報】【最新の法改正情報】から【助成金関連情報】まで、当サイトにある全ての記事内容を閲覧することができます。

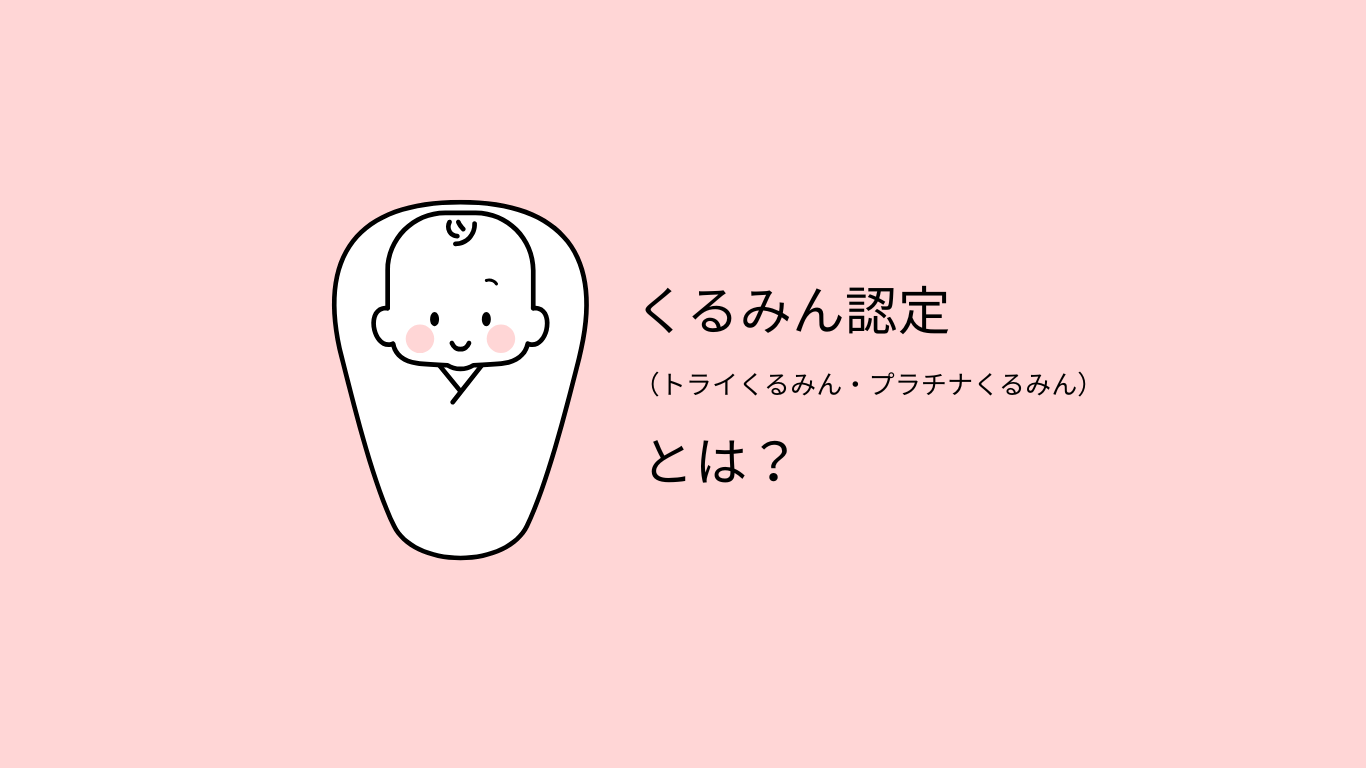
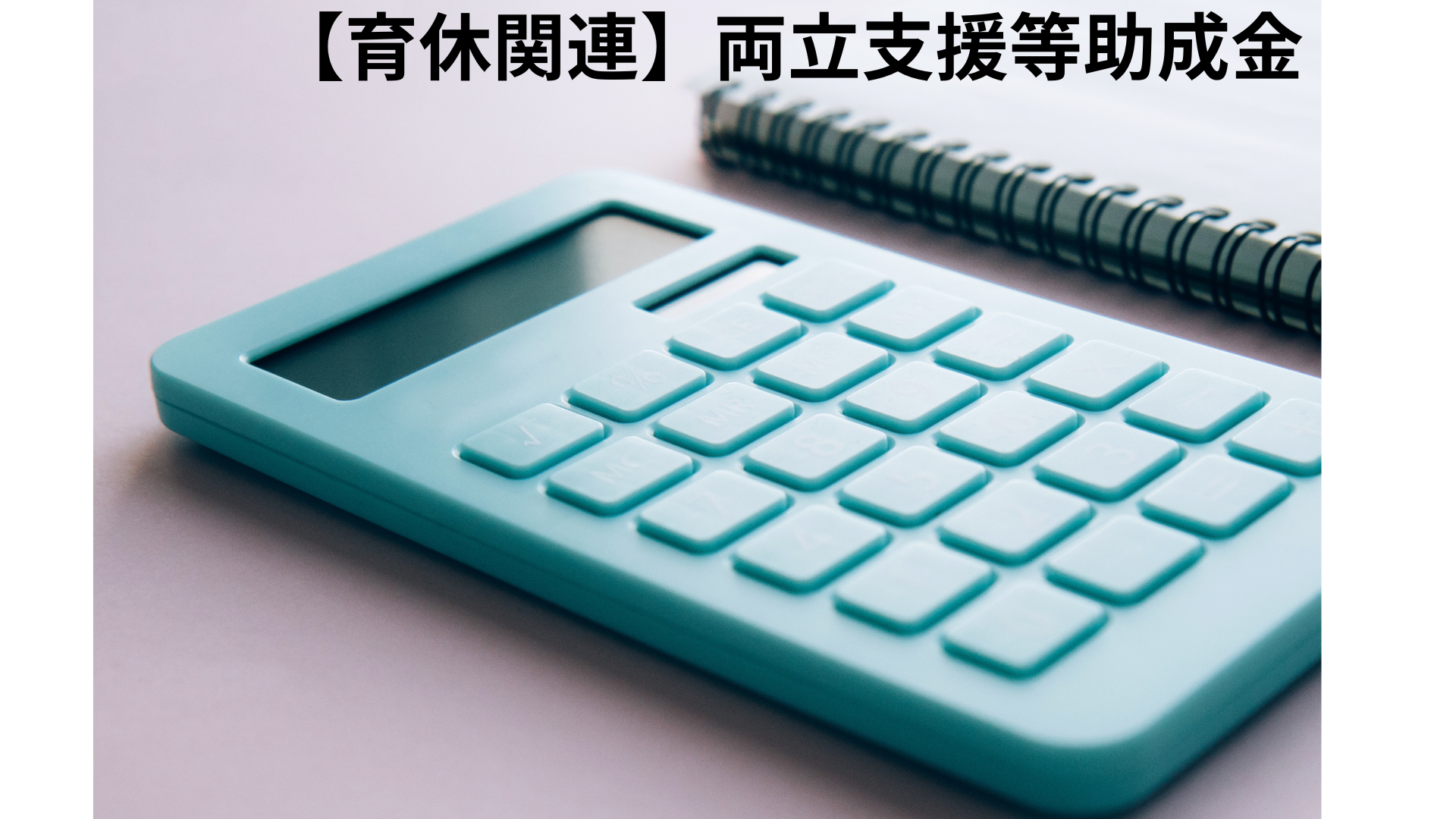


②.png)