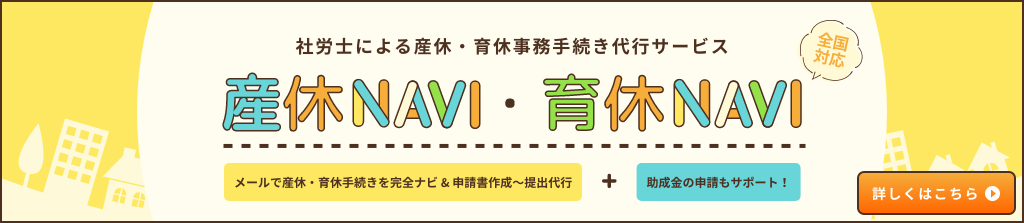この記事では、産前産後休業期間中に支給される、出産手当金の支給額・支給要件について、初心者でもインプットしやすいよう、わかりやすく解説しています。
<この記事はこんな方におすすめです>
✅産休・育休制度を知っておきたい会社経営者の方
✅初めて産休・育休手続きをする労務担当者の方
✅これから産休・育休の利用を考えている社員の方
✅産休・育休制度の内容を、おさらいしたい方
✅産休・育休制度の最新情報を知りたい方
はじめに
社員の方から初めて産休や育休をとりたいと相談があった場合、ピンチヒッターの確保に加えて、最も気になるのは、以下についてではないでしょうか?
■休業期間中の給与支払いはどうすべきか?
■休業期間中に支給される手当金や給付金制度の内容は?
この記事では、上記を踏まえた上で、産休期間中に支給される出産手当金の内容について、わかりやすく解説していきます。
令和4年4月1日より育児介護休業法が改定され、企業規模の大小を問わず、本人又は配偶者等の妊娠・出産を申出した労働者に対し「育休取得の意向確認」「制度内容の個別周知」を行うことが義務化されました。
この定めは、あくまでも育休制度についてのものではありますが、産休の取得を希望する労働者から申出があれば、当然、産休に関する制度内容についても同時に説明すべきものであると捉えるのが自然です。
よって、会社手続き担当者の方は育休に関する制度のみならず、産休関連の制度についても、社員の方へ誤った説明をしてしまわないよう、事前にしっかり理解しておく必要があります。
もちろん、この記事は、これから産休を取得予定の従業員の方ご本人がお読みいただいても結構です。
会社担当者の立場から制度を理解できますので、分かりやすいかと思います。
当事務所では、小規模企業でも産休・育休手続きを円滑に進められるよう・・・
産休・育休手続ナビゲーション+申請手続代行サービスを
顧問契約不要・安心の一括スポット料金でご提供しております。
メールのみで・・・
- お申込み(別途 書面の郵送が必要となります)
- 最新の産休・育休制度情報収集
- 産休・育休、各種事務手続のアウトソーシング
まで、一筆書きで完了させることができる画期的なサービス内容となっております。
あわせて・・・
- 育休関連助成金の申請サポート【事前手数料なし / 完全成果報酬制】
- 助成金サポートのみ お申込みもOK
にも対応しております。(東京しごと財団 働くパパママ育業応援奨励金 の併給申請サポートも可能です)
完全オンライン対応で、就業規則等改定~助成金(奨励金)申請代行まで個別にサポート致します。
- 産休・育休取得実績が乏しい小規模企業のご担当者様
- ご多忙につき、「情報収集の時間確保」が難しいご担当者様
- 業務中断せず、自分のペースで支援を受けたいご担当者様
から大変ご好評いただいております。
【全国47都道府県対応】
メールで気軽に支援が受けられる!
当サービスをご利用いただくと、以下1~7の全てを、一筆書きで完了させることができます。
- 産休・育休申出者への相談対応に必要となる最新の制度情報収集
- 休業申出書・育休取扱通知書等、各種必要書面の準備
- 切迫早産・切迫流産等発生時の傷病手当金(*)申請
- 出産手当金(*)・育休給付金・社会保険料免除等、産休・育休に必要な全ての申請(手続代行)
- 社会保険料引き落しの停止や地方税徴収方法変更等、給与支払事務の変更手続
- 職場復帰後の「休業終了時 社会保険料特例改定」(手続き代行)
- 「厚生年金保険料 養育期間特例適用」申請(申請書作成のみサポート)
(*)電子申請できない書類は書面作成のみサポート致します。

CLASSY. 2024年2月号に掲載されました
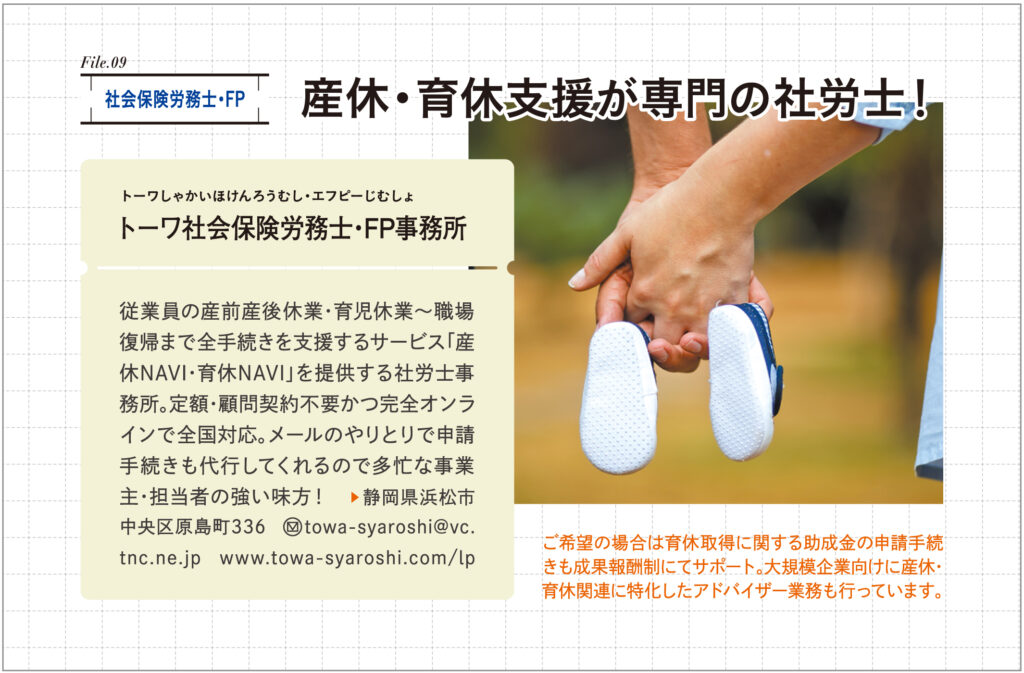
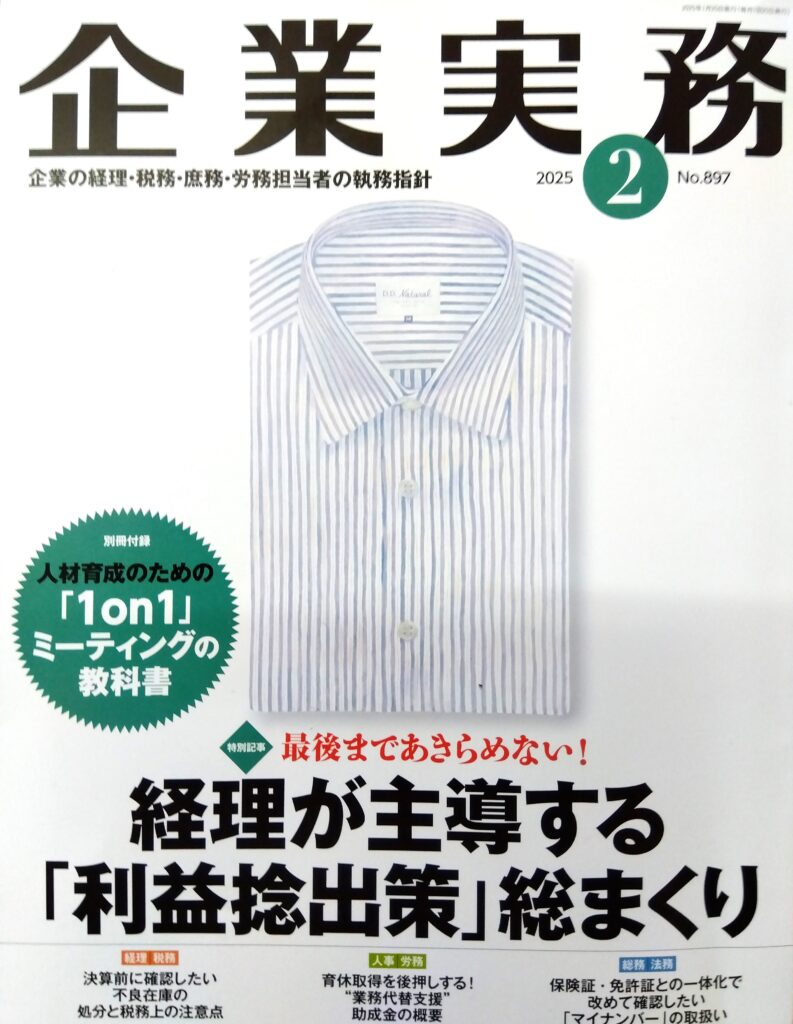
企業実務2025年2月号に寄稿させていただきました
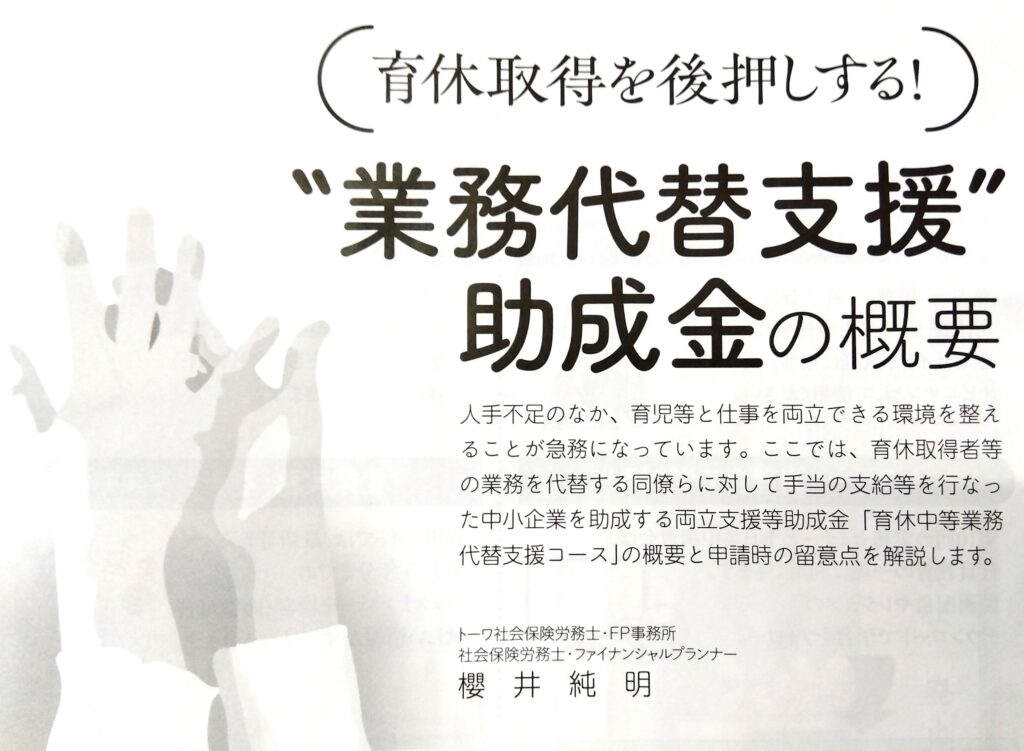
【両立支援等助成金・東京都奨励金 活用のご案内】
従業員の育休取得を推進する中小企業に対しては、非常に手厚い助成金・奨励金制度が設けられています!
育休関連の助成金・奨励金制度について知りたい方は、以下のサイトもご参照下さい。
欠員補充コストでお悩みの事業主様には、是非とも知っておいていただきたい内容となっています。
産休・育休関連情報 総合ページへのリンクはこちら!
以下のページからアクセスすれば、産休・育休関連の【各種制度・手続き情報】【最新の法改正情報】から【助成金関連情報】まで、当サイトにある全ての記事内容を閲覧することができます。
産休・育休期間中の給与支払いはどうすべきか?
さて、まずは、産休・育休期間中の給与支払いはどうすべきか?について解説していきましょう。
結論から言いますと、産休・育休期間中の給与は一般的には無給とします。
理由は、以下のとおりです。
給与を払うと、手当金や給付金が減額される仕組みがある
産休期間中は、休業する従業員の方が勤務先を通じて健康保険に加入している場合、出産手当金が支給されます。
育休期間中は、休業する従業員の方が勤務先を通じて雇用保険に加入しており、一定の条件を満たす場合、育児休業給付金が支給されます。
ただし、出産手当金・育児休業給付金ともに・・・
支給対象となる休業期間中に給与が支払われた場合は、その金額に応じて、手当金・給付金を減額もしくは無支給とする支給調整の仕組みが働きます。
また・・・
事業主には産休・育休期間中の給与支払い義務はありません。(就業規則等に給与支払いにつき定めがある場合は除きます)
せっかく、休業期間中の給与を支払っても、支給調整されてしまうばかりか、そもそも給与支払い義務自体がありませんので、無給とするのが一般的となっています。
なお、出産手当金の支給調整については後ほど詳しく解説します。
出産手当金とは?
さて、ここから本題に入らせていただきます。
出産手当金を一言で表しますと・・・
- 産前産後休業期間中の収入を支えるものとして
- 健康保険法に基づき
- 産休前給与の2/3程度を受給することができる
制度となります。
なお、出産手当金は「土日祝日」などの「所定休日」も全て支給対象日とし、暦日ベースで支給されます。
出産手当金を受給できない労働者もいる
先ほども解説しましたとおり、産休期間中は無給扱いとしている会社が一般的です。
これを補完するものとして、勤務先が加入する健康保険へ申請を行うことにより、出産手当金が支給される訳ですが・・・
産休は取得できても、支給対象とならない労働者がいる
場合があることには、注意しておかなければなりません。
どういうことなのか、詳しく見ていきましょう。
産休期間中には出産手当金が支給されるという話をしました。
しかし、これは、あくまでも健康保険法で定める・・・
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 健康保険組合
に加入している労働者に対しての話です。(一部の日雇い労働者は除きます)
産休は、労働基準法により母体保護を目的として定められているため、取得を希望する全ての労働者に与えなければならないことになっています。
一方、出産手当金は、健康保険法に定められた別制度の位置づけです。
よって、産休は取得できるが、出産手当金はもらえない労働者がいることとなります。
出産手当金を受給できない労働者
✅
配偶者など親族の加入する健康保険の扶養家族(=被扶養者)となっている労働者
✅
自分で国民健康保険に加入している労働者(一部の国民健康保険組合加入者は除く)
✅
勤務先の健康保険に加入する日雇い労働者の内、出産月の前4カ月間において26日分以上、保険料を納付していない労働者
上記労働者の方々には、原則、出産手当金の支給が行われません。
よって・・・
・パートやアルバイト等、短時間で働いている人
・飲食・理美容業等の業種で、勤務先の健康保険加入が強制となっていない個人事業主の元で働いている人
・日雇い勤務で働いている人
は、勤務先の健康保険へ加入しているか?や出産手当金の支給対象となっているか?についての再チェックを最初にしておく必要があります。
なお、例外として、同種同業の組合員で組織された国民健康保険組合等に加入している労働者の一部には、組合独自の定めで、出産手当金が支給される場合があります。
よって、国民健康保険に加入している社員に対しては、加入先の国保から出産手当金が支給されるのか否か、念のため事前確認しておくよう伝えておいたほうがよいかもしれません。
支給のタイミングについて
次に支給のタイミングについてですが、一般的には、産休が終了してから1か月以上後の支給になることがあると理解しておいて下さい。
ちなみに、申請が通った後の支給方法は、本人が届出した指定銀行口座への一括振込入金となります。
産前および産後休業期間中に複数回に渡り申請を行えば支給を早めることができますが、事務手続きが煩雑になりますので、休業する社員の方から特別に要望がある場合のみ対応している事業者が多いのが現状です。
支給を早めるために手続きした場合であっても、1カ月くらい後の支給になると考えておいたほうが無難です。
この支給時期については、産休予定の社員の方には、当面の収入のこともありますので、早めに伝えておいてあげたいところです。
では、なぜ、遅くなってしまうのでしょうか?
理由は、「支給されるまでに」というよりも「申請できるようになるまでに」時間がかかることにあります。
時間がかかるポイントとしては以下の2点が挙げられます。
✅
申請時点で、実際に休業した日が確定していなければならず、休業予定の段階では申請できないこと
✅
産休取得日が属する賃金締切り期間が過ぎてからでないと、勤務先による「休業した日に対する賃金支払い有無の証明」がスムーズに行えない場合があること(*)
(*)
全国健康保険協会の場合、従前は、賃金締切り期間を経過してからでないと出産手当金の申請自体ができないルールになっていましたが、令和5年1月以降の申請書式簡素化にともない、支給対象日を経過していれば提出できるよう、申請要件が緩和されました。
出産手当金の申請方法
それでは、出産手当金の具体的な申請方法について見ていきましょう。
申請先
出産手当金を受給するためには、「出産手当金支給申請書」を勤務先を管轄する全国健康保険協会(協会けんぽ)支部あてに申請します。
勤務先が健康保険組合へ加入している場合は加入先の健保組合へ申請します。
支給申請を行うタイミング
先ほども解説しましたが、出産手当金の申請は、申請時点で、実際に休業した日が確定していなければなりません。
よって、出産手当金の申請手続は、産休終了後に行われるのが一般的です。
出産証明の受入
この申請を行うためには、「出産手当金支給申請書」の所定欄に、出産したことの証明を受入する必要があります。
この証明は、休業者本人が、出産先医療機関の担当医師あるいは助産師に記入を依頼します。
休業期間中の給与支払い状況の確認
出産証明受入後は、勤務先から申請を行うのが一般的です。
勤務先は、本人から提出された申請書の所定欄に、休業期間中の給与支払い状況を記載・証明し、全国健康保険協会支部(あるいは健康保険組合)へ申請を行います。
急ぎで申請する場合の留意点
申請を急ぎたい場合、産休が終了する前であっても申請を行うことはできます。
ただし、申請日より前の休業済期間のみが支給申請の対象となり、この期間の賃金支払状況についても勤務先の証明が行われていなければなりません。
なお、残りの休業期間分については、2回目以降の申請として、改めて手続きを行う必要があります。
出産前に申請する場合は、出産予定証明の受け入れも必要
出産前に申請を行う場合は、申請書の出産証明欄に、出産予定日と胎児数についての証明も受入れしなければなりません。
後日、出産後の期間分を申請する際には、改めて出産したことの証明を受入する必要がありますので注意が必要です。(出産したことの証明は1度受入済であれば、それ以後に申請する際は不要となります)
上記説明のとおり、複数回の申請を繰り返すと事務負担が大きくなるばかりか、各証明について医療機関から文書料の支払いを求められる場合もあり、出費が増えることも考えられますので、不要不急の場合でなければ、なるべく産休終了後1回にまとめて申請したほうがよいでしょう。
出産手当金支給申請書の書き方
出産手当金支給申請書の書き方について知りたい方は、以下の記事をご参照下さい。
支給期間について
それでは引き続きまして、支給期間について解説していきます。
産休期間は最長で産前約6週間、産後は8週間
まずは、労働基準法の産前産後休業期間から見ていきましょう。
産休期間は・・・
- 産前休業期間
- 産後休業期間
に分かれます。
産前休業は、出産予定日の6週(多胎妊娠14週)間前から請求可能となっていますが、必ず6週(14週)間前から取得しなければならないものではなく、妊娠中の労働者本人からの請求に基づき開始します。
対して、産後休業は出産日の翌日から8週間となっており、原則、就労禁止です。
ただし、以下の要件を満たす場合は就労することが可能となっています。
- 産後6週間が経過していること
- 本人が就労を希望していること
- 医師が認める業務への就労であることの証明が提出されていること
次に、産前休業・産後休業日数を数える際の起算日についてです。
・産前休業は「出産予定日」から・・・
・産後休業は「実際の出産日」の翌日から・・・
カウントします。
つまり、出産日当日=産前期間となりますので、労働者本人から請求がなければ、ルール上は出産日当日の就労も可能ということになっています。
労働基準法と健康保険法では産前休業期間の考え方が若干異なる
当初の出産予定日と実際の出産日にズレが生じた場合、労働基準法の産前休業期間は長くなったり短くなったりします。
それに応じて、通例は、出産手当金の支給日数も多くなったり少なくなったりします。
つまり、労働基準法も健康保険法も基本的な産前産後休業期間の考え方は同じです。
ただし、予定日より前に出産となるケースについてのみ、健康保険法独自の取り決めが適用されるケースがあります。
どのようなことなのか、詳しく見ていきましょう。
健康保険法では・・・
産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
を産休期間としています。
ここで気を付けておかなければならないポイントは、産休期間を出産予定日からではなく、実際の出産日から起算している点です。
(ただし、予定日より遅く出産した場合は、当初の出産予定日から起算する決まりになっています)
・労働基準法の産休期間は、出産予定日から起算していますので、予定より早く出産すると短くなります。
・対して、健康保険法で定める産休期間は、実際の出産日から起算しますから短くなるとは限りません。
何を言いたいかというと・・・
出産が予定日より早まった分の日数を当初の産休開始日から繰上げて、再判定した中に・・・
「妊娠・出産のため労務に服さなかった」日があれば、その日も産休期間≒出産手当金の支給対象に含めることができる
ということです。
例えば、当初産休開始日の直前に、所定休日、欠勤日をくっつけているような場合がこれにあたります。
ちなみに、これらの日が当初産休開始日と連続していなければならないルールはありません。
ただし「妊娠・出産のため労務に服さなかった日」でなければ、産休期間に含めることはできません。
では、当初産休開始日の直前に年次有給休暇を取得していた場合はどうなるでしょうか?
年次有給休暇を取得している日についても産休期間に含めることはできます。
ただし、年次有給休暇の取得日に対しては給与が支給されますので、冒頭で解説したとおり、その金額によっては出産手当金が無支給となるか、もしくは減額支給されることとなります。
次に、予定日よりも遅く出産した場合について解説します。
この場合は・・・
当初産休開始日を繰り下げる必要はなく、従前どおり出産予定日から起算して産前休業期間を数える
こととなっています。
予定より早く出産した場合のように、産前休業期間の再判定を行う必要は生じません。
つまり、予定より遅れた分、産前休業期間は長くなり、その分、出産手当金の支給対象日数も多くなるということです。
支給額について
さて、ここからは、支給額について解説していきます。
まず・・・
・出産手当金は日額ベースで支給される
ということを踏まえておきましょう。
支給日額×支給日数=支給総額が、届出した預金口座へ後日、一括振込されることとなります。
それでは、具体的な日額計算方法について見ていきましょう。
なお、以下で解説する計算方法は、全国健康保険協会(協会けんぽ)加入企業の場合となります。
健康保険組合加入企業の場合は、加入先組合の定めにしたがって下さい。
出産手当金の支給日額は・・・
・支給開始日以前における、連続した12カ月間の各月の標準報酬月額平均額÷30日分×2/3
となります。
なお、端数計算については・・・
÷30日した後の端数は →10円未満四捨五入
×2/3 した後の端数は → 円未満四捨五入
とします。
ここでのポイントは、標準報酬月額が計算のベースとなっている点です。
実際に支給された給与額をベースにするわけではありませんのでご注意下さい。
また、支給開始日以前の連続した12か月間に、標準報酬月額が改定されている場合は、12か月の平均額を計算のベースとする点にも注意が必要です。
標準報酬月額の仕組みについて知りたい方は、以下、協会けんぽのホームページをご参照下さい。
なお、健康保険組合(組合けんぽ)では、出産手当金の付加給付(増額支給)を行っている場合があります。
各組合ごとに独自の取り決めをしていますので、加入先が健保組合の場合は、必ず付加給付の有無についても確認しておきましょう。
(全国健康保険協会〔協会けんぽ〕には、付加給付の制度はありません)
協会けんぽ加入後12カ月に満たない場合の計算方法
では、健康保険に加入してから12か月に満たない社員が産休を取得した場合、出産手当金はどのように計算するのでしょうか?
この場合は・・・
・12カ月に満たない部分の、各月の標準報酬月額平均額
・全国健康保険協会が別途発表する、全加入者の標準報酬月額平均額(令和6年度=30万円)
のうち、いずれか小さい額÷30日分×2/3を支給日額とします。
支給調整について
冒頭でも触れましたとおり、出産手当金には、支給対象となる休業期間中に給与が支払われた場合、その金額に応じて、手当金・給付金を減額もしく無支給とする支給調整の仕組みがあります。
ここでは、この支給調整の内容について具体的に解説していきます。
まず、支給調整についても日額ベースで行われるということを踏まえておきましょう。
その内容は・・・
「給与日額 > 出産手当金日額」の場合は不支給
「給与日額 < 出産手当金日額」の場合は「出産手当金日額 ー 給与日額」を支給
となっています。
休業期間の一部の日のみを対象として給与が支払われた場合は、当該支給総額÷支給対象日数によって給与日額を算定します。
賃金締め切り期間の途中から休業開始しているものの、日割り控除が行われず月額として満額が支払われているようなケースでは、出産手当金日額の算定とフェーズを合わせるため、当該支給額÷30日をもって給与日額とします。
ちなみに、「通勤手当」や「住宅手当」「扶養手当」など、毎月「固定額」を支給している手当についても、休業対象日を含む賃金締め切り期間について休業日数に応じた日割り控除が行われていない場合には、上記同様の算定式により支給調整の対象となります。
賞与を支給した場合
出産手当金の支給対象期間中に賞与を支給した場合はどうなるでしょうか?
この場合は、支給調整されずに出産手当金の全額を受給することができます。
逆に、産休の取得を理由に賞与を減額もしくは支給しないことは、男女雇用機会均等法第9条で禁止されていますので、こちらを注意しなければなりません。
一般的に、賞与の支給内容には会社全体の業績や従業員毎の貢献度等が色濃く反映されますので、妊娠や出産の有無にかかわらず減額査定となることは十分考えられます。
ただし、産休・育休の取得そのものがマイナス評価につながっているような支給内容は、不利益取扱いとみなされます。
ちなみに、算定対象期間から産休・育休期間を除いたことにより、当該日数分、減額支給となることには何ら問題ありません。
会社役員でも出産手当金を受給できる
会社役員は労働基準法が適用されないため、労働基準法に定められた産休制度も適用対象外となっています。
しかしながら、勤務先の健康保険に加入している会社役員は、通常の労働者と同じく、
産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
について出産手当金を受給することができます。
その理由は、出産手当金については・・・
労働基準法の適用有無に関係なく、受給要件を満たす健康保険加入者であれば、その全てが出産手当金の受給対象者
となっているからです。
会社役員の産休取得時には定期同額給与(役員報酬)の支払い停止も検討しておく
会社役員の報酬が税務処理上、損金(会社経費)として認められるためには「定期同額給与」としての支払いが必要となります。
「定期同額給与」は株主総会等であらかじめ金額が決定されるもので、1か月以下の一定の期間ごとに同額を支給するものでなければならず、産休取得日についての日割り控除を行うことはできません。
このため、会社役員の方が産休を取得するにあたり、出産手当金を受給したいのであれば、顧問税理士先生等へあらかじめ相談し、当該期間中の役員報酬支払を停止する等の手続き(臨時株主総会の開催等が前提)を行っておく必要があります。
なぜなら、産休期間中に支払われた役員報酬は、出産手当金の支給調整対象となってしまうからです。
会社役員は育休時の育児休業給付金を受給できない
少し横道にそれますが、会社役員の場合、育児休業給付金は受給できるのでしょうか?
答えは×で、受給できません。
その理由は・・・
育児休業給付金は雇用保険法の制度
であるからです。
会社役員には雇用保険が適用されず、日頃から雇用保険料も支払っていませんので、仮に育児のために休業したとしても育児休業給付金を受給することはできません。
ただし、例外として雇用保険に加入している使用人兼務役員については、育児休業給付金を受給することができます。
任意継続被保険者は、出産手当金を受給できない
ここからは、健康保険任意継続被保険者の取扱いについてです。
任意継続被保険者制度とは、会社を退職した後も健康保険料を全額自己負担により支払い続ければ、最長2年の間、離職した会社の健康保険に加入し続けられる制度です。
任意継続被保険者であっても、(健康保険への加入義務がない)個人事業主のもとへ再就職し、その後産休取得に至ることがないとも限りません。
このような場合、全国健康保険協会(協会けんぽ)では・・・
任意継続被保険者は出産手当金の支給対象外
としています。
健康保険の適用外である事業所での産休取得であるため、出産手当金についても支給対象外になっていると考えれば分かりやすいかもしれません。
なお、健康保険組合の場合は独自の定めがあるかもしれませんので、念のため加入先の組合へ確認しておいたほうがよいでしょう。
妊娠85日以後の流産・人工妊娠中絶の場合も支給対象となる
労働基準法では、「出産」について以下のように定めています。
- 妊娠85日以後の出産(早産を含む)
- 妊娠85日以後の死産(流産)
- 妊娠85日以後の人工妊娠中絶
上記に該当した日は全て出産日とみなしますので・・・
その産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
についても出産手当金の支給対象となります。
産休中やむを得ず離職する場合
最後に、産休中に離職してしまった場合の取扱いについてです。
健康保険法では、出産予定日前42日(多胎妊娠98日)を過ぎてから離職する場合についても・・・
産前休業開始日から、産後56日間全てに対する出産手当金を受給することができる
としています。
ただし、受給要件として・・・
・連続して1年以上、健康保険に加入している
・退職日に出勤していない
ことの2点を両方とも満たしていなければならないとされています。
事業主の方にとっては、産休もしくは育休を取得し、職場復帰する予定であった社員が、思いがけず離職してしまうのですから、心中穏やかではないかもしれません。
ピンチ要員確保等の手配も行っていることを考慮すれば尚のことです。
あえて手当金を受給させてあげようと、会社から働きかけるケースがあるかもしれませんが、この場合は制度趣旨から外れることとなります。
ですので、表題はあくまでも、「やむを得ず離職する場合」とさせていただきました。
当然ながら、受給する労働者の側も、もともと離職するつもりでいて休業の申出をし、この特例を利用するのは慎むべきことだと思います。
なお、この場合も・・・
・医師・助産師による出産証明
・勤務先による「産休期間中の賃金支払い実績」の証明
がなければ出産手当金の申請をすることはできません。
また、出産手当金の受給期間中については雇用保険から失業給付を受給することはできないことも併せて確認しておきましょう。
まとめ

今回は、産休中の収入補助である、出産手当金について解説してきました。
意外にも、気を付けておくべきポイントがたくさんあることに驚かれたのではないでしょうか?
手続きを進める際には、この記事を再読し、ぜひ活用していただければと思います。
当事務所では、小規模企業でも産休・育休手続きを円滑に進められるよう・・・
産休・育休手続ナビゲーション+申請手続代行サービスを
顧問契約不要・安心の一括スポット料金でご提供しております。
メールのみで・・・
- お申込み(別途 書面の郵送が必要となります)
- 最新の産休・育休制度情報収集
- 産休・育休、各種事務手続のアウトソーシング
まで、一筆書きで完了させることができる画期的なサービス内容となっております。
あわせて・・・
- 育休関連助成金の申請サポート【事前手数料なし / 完全成果報酬制】
- 助成金サポートのみ お申込みもOK
にも対応しております。(東京しごと財団 働くパパママ育業応援奨励金 の併給申請サポートも可能です)
完全オンライン対応で、就業規則等改定~助成金(奨励金)申請代行まで個別にサポート致します。
- 産休・育休取得実績が乏しい小規模企業のご担当者様
- ご多忙につき、「情報収集の時間確保」が難しいご担当者様
- 業務中断せず、自分のペースで支援を受けたいご担当者様
から大変ご好評いただいております。
【全国47都道府県対応】
メールで気軽に支援が受けられる!
当サービスをご利用いただくと、以下1~7の全てを、一筆書きで完了させることができます。
- 産休・育休申出者への相談対応に必要となる最新の制度情報収集
- 休業申出書・育休取扱通知書等、各種必要書面の準備
- 切迫早産・切迫流産等発生時の傷病手当金(*)申請
- 出産手当金(*)・育休給付金・社会保険料免除等、産休・育休に必要な全ての申請(手続代行)
- 社会保険料引き落しの停止や地方税徴収方法変更等、給与支払事務の変更手続
- 職場復帰後の「休業終了時 社会保険料特例改定」(手続き代行)
- 「厚生年金保険料 養育期間特例適用」申請(申請書作成のみサポート)
(*)電子申請できない書類は書面作成のみサポート致します。

CLASSY. 2024年2月号に掲載されました
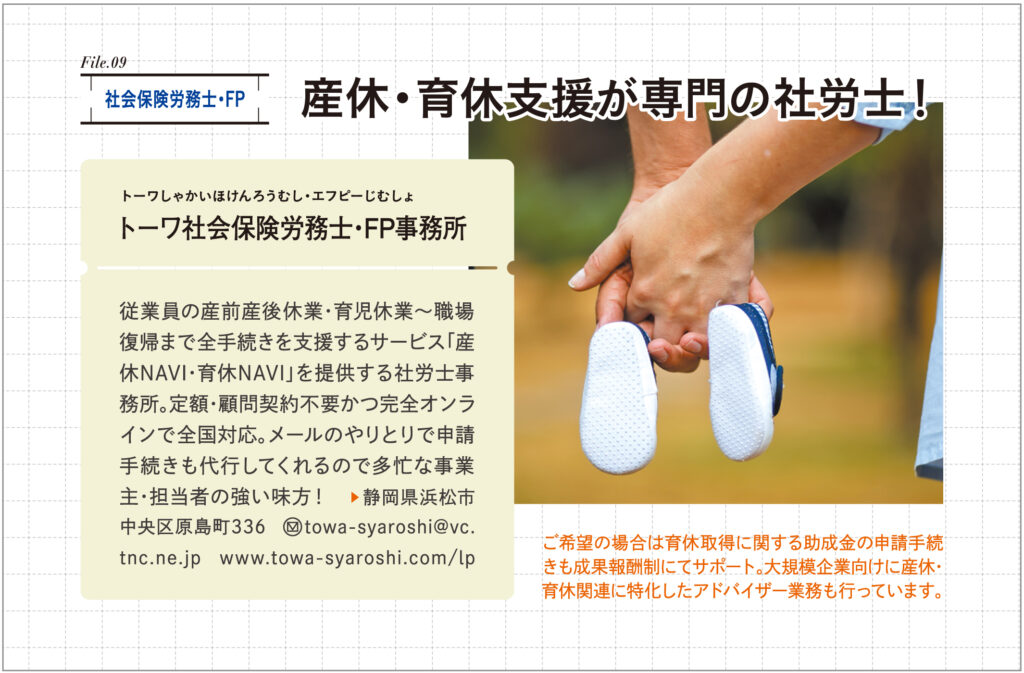
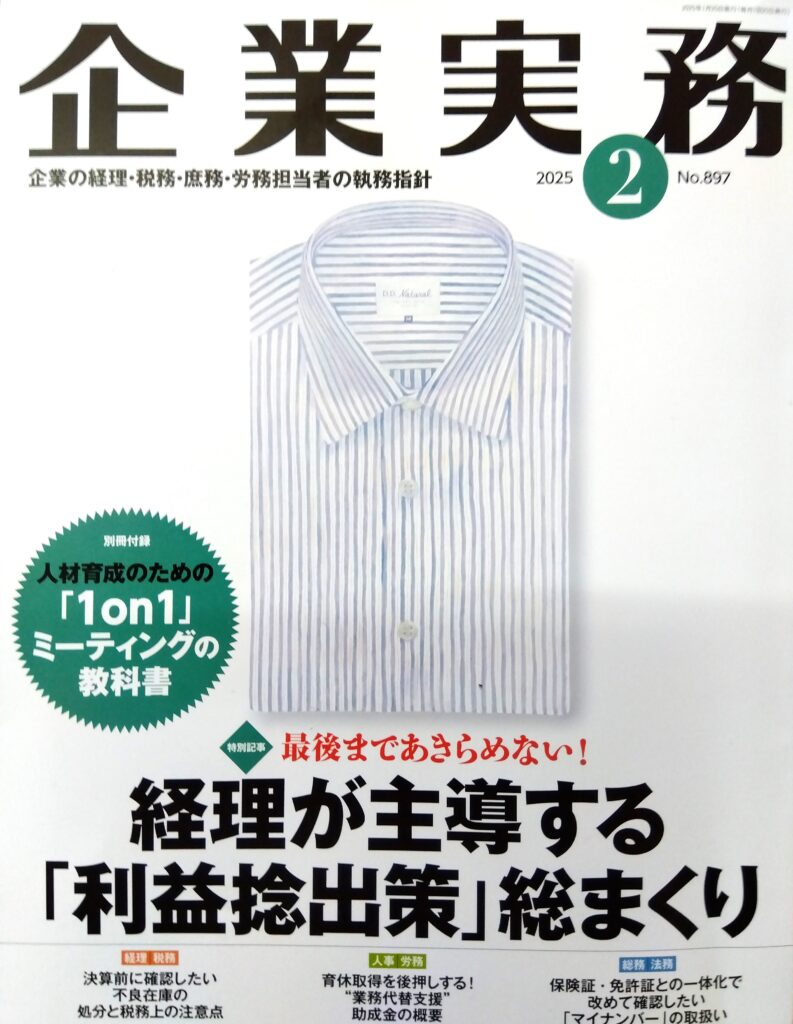
企業実務2025年2月号に寄稿させていただきました
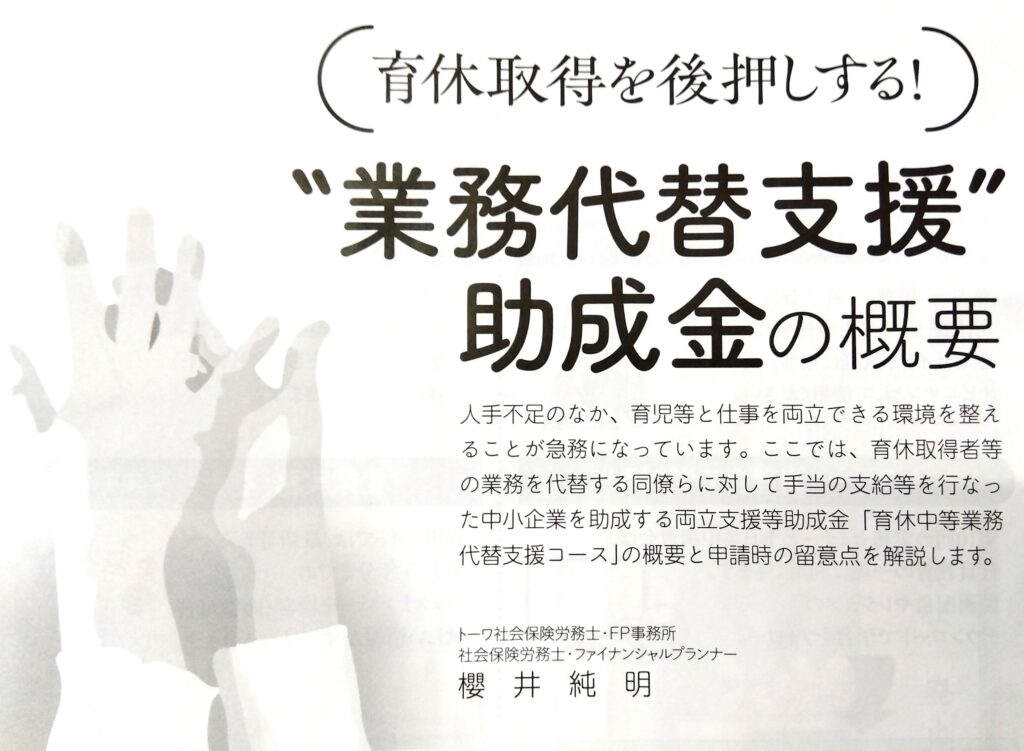
【両立支援等助成金・東京都奨励金 活用のご案内】
従業員の育休取得を推進する中小企業に対しては、非常に手厚い助成金・奨励金制度が設けられています!
育休関連の助成金・奨励金制度について知りたい方は、以下のサイトもご参照下さい。
欠員補充コストでお悩みの事業主様には、是非とも知っておいていただきたい内容となっています。
産休・育休関連情報 総合ページへのリンクはこちら!
以下のページからアクセスすれば、産休・育休関連の【各種制度・手続き情報】【最新の法改正情報】から【助成金関連情報】まで、当サイトにある全ての記事内容を閲覧することができます。



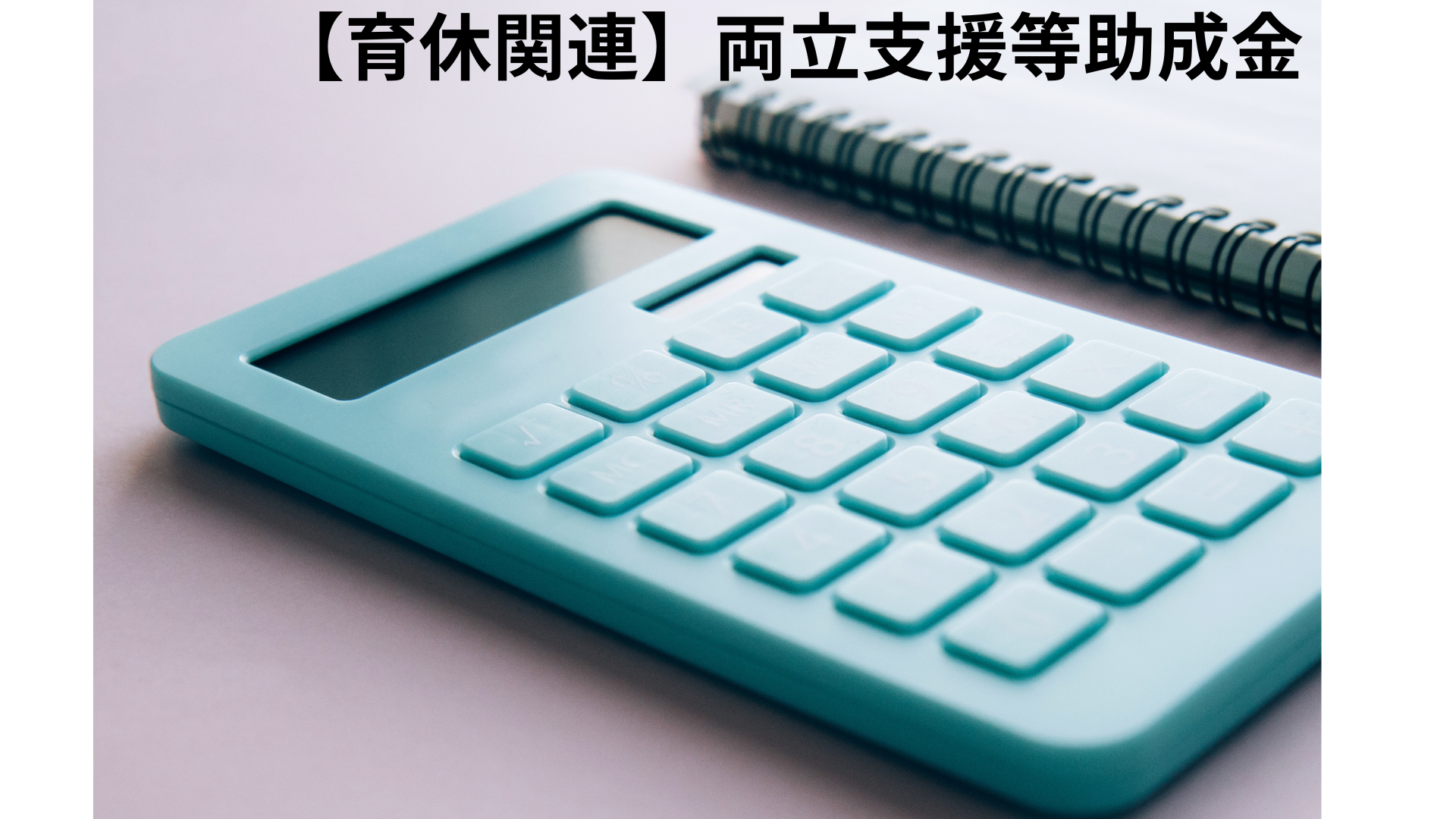


②.png)