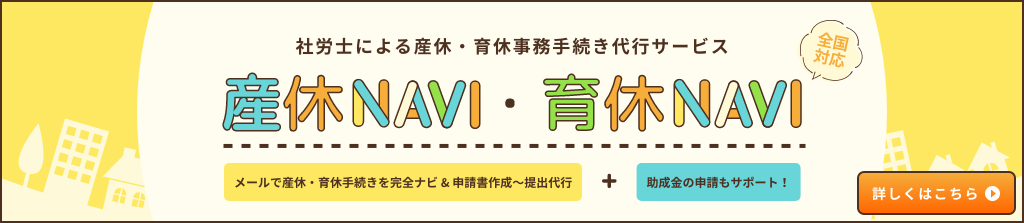■このページでは、雇用保険から支給される「育児休業給付金」の概要とその申請方法について解説しています。
(なお、船員保険に加入する方、および共済組合等に加入する公務員の方は対象から除いて解説していきますのでご了承下さい)
令和4年10月1日より制度運用がスタートした「出生時育児休業給付金」については以下の記事をご参照下さい。
目次
- 育休期間中の給与支払いについて
- 育児休業給付金について
- 育児休業期間中に雇用保険資格の得喪があった場合
- 育児休業給付金の支給対象者
- 育児休業は取得できても、育児休業給付金の支給対象とならない労働者がいる
- 育児休業給付金の支給対象外となる方
- 育児休業給付金申請~支給のタイミング
- 支給額について
- 育休開始から181日目以降の月額支給額
- 多胎出産でも育児休業給付金は増額されない
- 支給期間について
- 育児休業給付金の支給調整(不支給となる場合)
- 育休給付金の支給調整(減額支給の場合)
- 減額支給となる場合の支給調整例
- 賞与を払っても給付金は減額されない
- 育児休業給付金の申請の仕方
- 育児休業を分割取得する場合の申請方法
- 育休期間中の従業員を転籍させる場合の給付金申請方法
育休期間中の給与支払いについて
育休期間中の給与は一般的には無給とします。
理由は・・・
給与の支払いを行うと、休業期間中に支給される給付金が減額される仕組みがある
ためです。
休業する従業員の方が雇用保険に加入し一定の条件を満たしている場合、「育児休業給付金」を受給することができます。
一方、支給対象となる休業期間中に給与が支払われると、その金額に応じて給付金は「無支給」又は「減額支給」となる場合があります。
くわえて、事業主には・・・
「育休期間中の給与支払義務」はありません(*)
(*)就業規則等で給与支給について定めがある場合は除きます
よって、育児休業期間中の給与を支払わない企業が大半を占めることになっています。
(育児休業給付金の支給調整については後ほど詳しく解説します)
それでは、具体的な育児休業給付金の内容について見ていきましょう。
育児休業給付金について
育児休業給付金とは
- 育児休業期間中の収入を支えるものとして
- 雇用保険法に基づき
- 休業開始日から180日間は休業前給与額(*)の2/3(67%)程度、それ以降は1/2(50%)程度を受給できる
制度となっています。
ただし、退職予定の場合や、その他要件を満たしていない場合には支給されません。
(*)上限額が設定されていますので、高収入の対象者へ説明する際には注意が必要です
出生後休業支援給付金の上乗せ支給が開始(令和7年4月1日以降)
なお、令和7年4月1日以降は、子の出生直後の一定期間内において、両親ともに14日以上の育児休業(出生時育児休業を含む)を取得した場合、28日分までを上限に、出生後休業支援給付金として、(出生時)育児休業給付金にプラスして13%の上乗せ支給が行われます。
(配偶者が育休対象者でない場合等、特定の事情がある場合は、本人のみ14日以上の育休取得でも支給されます)
こちらの制度について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照下さい。
育児休業を分割取得した場合
育児休業は2回に分割して取得することができますが、「育児休業給付金」の支給申請についても、それぞれの期間について行うことができます。
なお、以下の通り、やむを得ない理由により3回目以降の育児休業取得が認められる場合がありますが、その休業期間についても「育児休業給付金」の支給申請を行うことができます。
育休の3回目以降取得が認められる場合
〔例外①: 新たな産休・育休又は介護休業の開始により育休を途中終了した場合〕
新たな産休・育休又は介護休業の開始により「育休を途中終了」した場合で、新たな産休・育休に係る子や介護休業に係る対象者が死亡した場合、他人の養子としたことによりその子と同居しなくなった場合については、3回目の再取得が認められます。
〔例外②:養育対象児の負傷・疾病・精神障害〕
子が1歳に到達する前に「2回目の育休」を終了して職場復帰したものの、養育対象となっていた子が負傷・疾病・精神障害の状態となり、2週間以上看護が必要な状態となった場合には、3回目の再取得が認められます。
〔例外③:子を養育する配偶者の死亡・負傷・婚姻の解消等〕
育休の申出対象である子の養育を行う配偶者が、死亡・負傷・婚姻解消等の理由により、子と同居しないこととなり、その養育ができなくなった場合等には 3回目の再取得が認められます。
〔例外④:養育する子を保育所等へ入園させられない場合等〕
2回目の育休を終了して職場復帰したものの、養育する子について、保育所等への利用申込みが通らず、当面その実施が行われない場合等には3回目の取得が認められます。
2回目の育休終了後、上記の事由に該当し、子の1歳誕生日から育休を延長して再取得する場合などが該当します。
ちなみに育児介護休業法上は、子が「1歳になるまでの育休」と「1歳から1歳6か月までの育休」および「1歳6か月から2歳までの育休」は別物の育休として考えます。
ですので、1歳誕生日から実質的に延長して再取得する育休は、厳密には3回目の取得としては数えません。
申出書についても「育児休業期間変更申出書」ではなく、新たな「育児休業申出書」を再受け入れするのが正しい手続き方法となります。(子が1歳6か月に到達し、2歳まで育休を実質的に再延長する際にも同様の手続きが必要となります)
なお、1歳以降に取得する育休は、1歳になるまでの育休のように分割して取得することが認められていません。
そのため、夫婦交替でこの育休を取得する場合の育児休業給付金申請は、「1歳から1歳6か月まで」と「1歳6か月から2歳まで」の各期間ごとに、夫婦それぞれ各1回までしか行うことができません。
育児休業期間中に雇用保険資格の得喪があった場合
育児休業期間中に勤務先の会社が買収され、買収先の企業が従業員の雇用をそのまま引き継ぐような場合があります。
このような場合、育児休業を取得中であった旧勤務先の雇用保険被保険者資格は喪失となり、買収先企業の雇用保険被保険者として新たな資格を取得することになります。
買収先企業に雇用が引き継がれる時には、そのまま育児休業を取得し続けられるのが通例ですが、この際、気をつけておかなければならないことがあります。
それは、旧勤務先で取得していた育児休業は終了となり、買収先企業では新たな育児休業を取得した扱いとなるため、本人の意思に関係なく、育児休業は旧勤務先で取得していたものが1回目、買収先企業で再取得したものが2回目といったように分割取得されたものとしてカウントされてしまうことです。
もし、旧勤務先で取得中であった育児休業が、(保育所へ入所出来なかったこと等を理由として)子が1歳6か月となるまで、もしくは子が2歳となるまでの間で延長して取得していたものであった場合は、買収先企業では、育児介護休業法に基づく育児休業の再取得はできないこととなってしまいます。
なぜなら、子の1歳以降に延長する育児休業は、育児介護休業法上、2回に分割して取得できない決まりとなっているからです。
また、上記のような場合において、仮に子が1歳6か月もしくは2歳になるまで、買収先企業が独自に付与する育児休業を取得できたとしても、育児介護休業法に基づく育児休業の取得ではないため、雇用保険法に基づく育児休業給付金の支給は受けられないこととなってしまいます。
もし、このようなケースが発生する場合には、買収先企業は、事前にその前後策について検討しておく必要があるといえます。
それでは引き続き、育児休業給付金の支給対象者について見ていきましょう。
当事務所では、小規模企業でも産休・育休手続きを円滑に進められるよう・・・
産休・育休手続ナビゲーション+申請手続代行サービスを
顧問契約不要・安心の一括スポット料金でご提供しております。
メールのみで・・・
- お申込み(別途 書面の郵送が必要となります)
- 最新の産休・育休制度情報収集
- 産休・育休、各種事務手続のアウトソーシング
まで、一筆書きで完了させることができる画期的なサービス内容となっております。
あわせて・・・
- 育休関連助成金の申請サポート【事前手数料なし / 完全成果報酬制】
- 助成金サポートのみ お申込みもOK
にも対応しております。(東京しごと財団 働くパパママ育業応援奨励金 の併給申請サポートも可能です)
完全オンライン対応で、就業規則等改定~助成金(奨励金)申請代行まで個別にサポート致します。
- 産休・育休取得実績が乏しい小規模企業のご担当者様
- ご多忙につき、「情報収集の時間確保」が難しいご担当者様
- 業務中断せず、自分のペースで支援を受けたいご担当者様
から大変ご好評いただいております。
【全国47都道府県対応】
メールで気軽に支援が受けられる!
当サービスをご利用いただくと、以下1~7の全てを、一筆書きで完了させることができます。
- 産休・育休申出者への相談対応に必要となる最新の制度情報収集
- 休業申出書・育休取扱通知書等、各種必要書面の準備
- 切迫早産・切迫流産等発生時の傷病手当金(*)、帝王切開時の高額療養費限度額適用認定(*)申請
- 出産手当金(*)・育休給付金・社会保険料免除等、産休・育休に必要な全ての申請(手続代行)
- 社会保険料引き落しの停止や地方税徴収方法変更等、給与支払事務の変更手続
- 職場復帰後の「休業終了時 社会保険料特例改定」(手続き代行)
- 「厚生年金保険料 養育期間特例適用」申請(申請書作成のみサポート)
(*)電子申請できない書類は書面作成のみサポート致します。

CLASSY. 2024年2月号に掲載されました
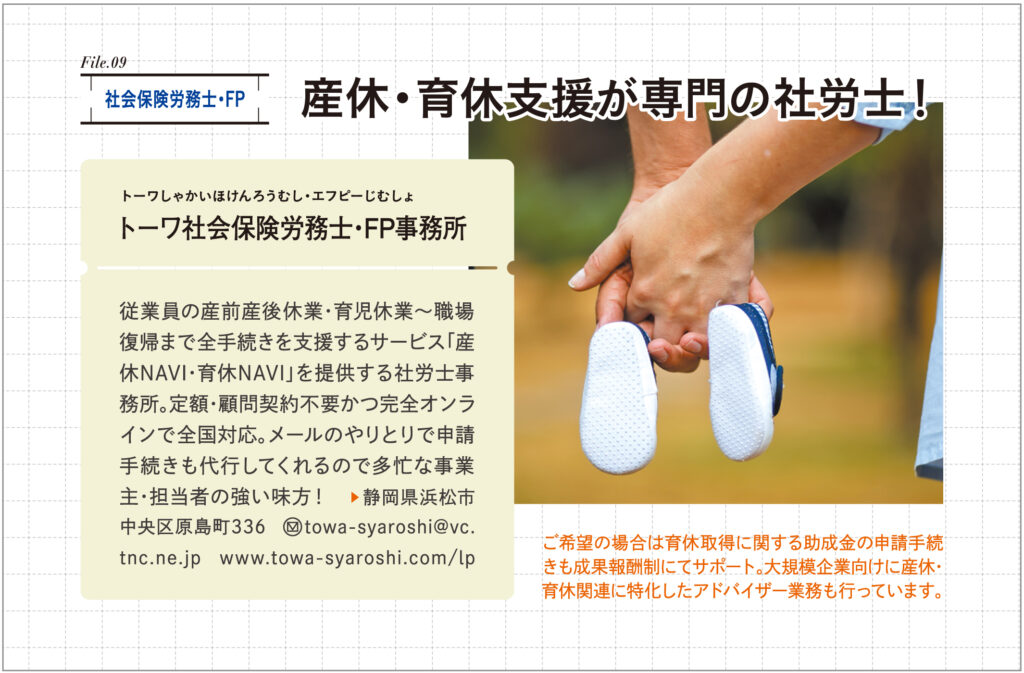
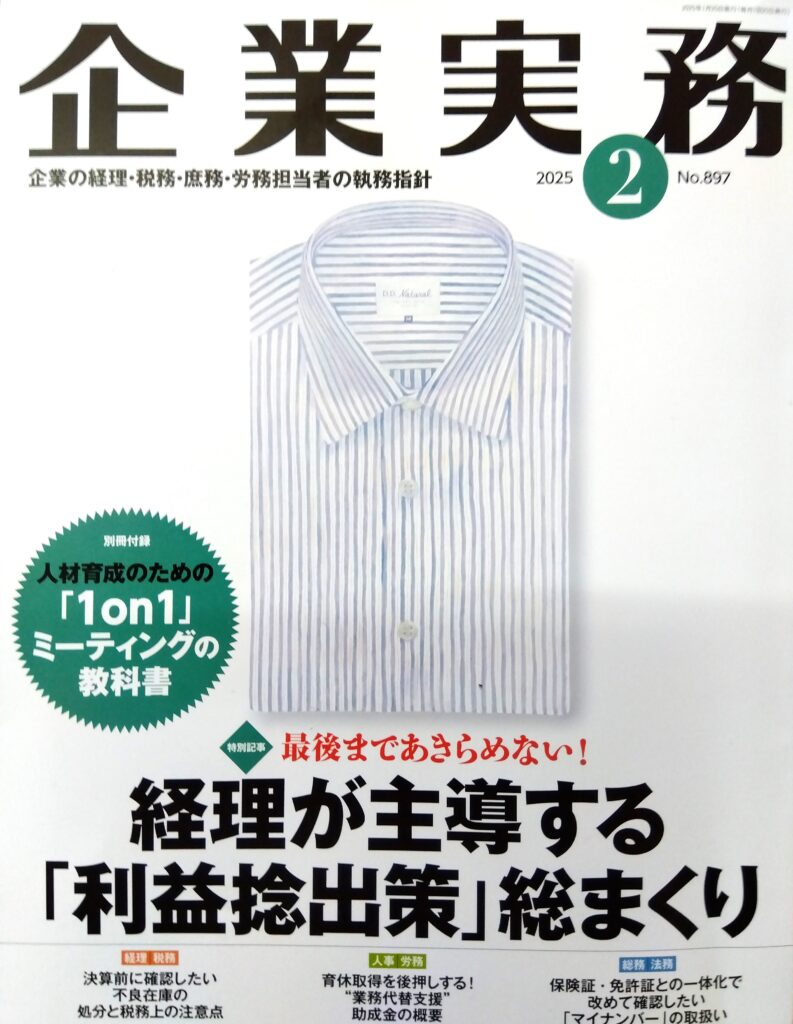
企業実務2025年2月号に寄稿させていただきました
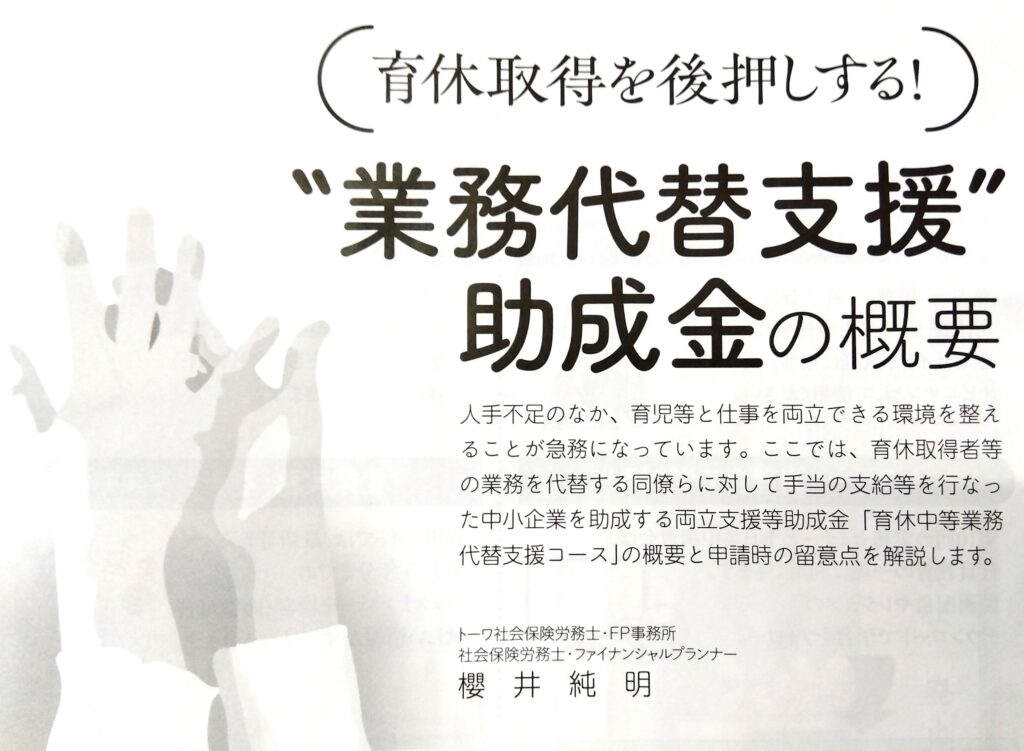
【両立支援等助成金・東京都奨励金 活用のご案内】
従業員の育休取得を推進する中小企業に対しては、非常に手厚い助成金・奨励金制度が設けられています!
育休関連の助成金・奨励金制度について知りたい方は、以下のサイトもご参照下さい。
欠員補充コストでお悩みの事業主様には、是非とも知っておいていただきたい内容となっています。
産休・育休関連情報 総合ページへのリンクはこちら!
以下のページからアクセスすれば、産休・育休関連の【各種制度・手続き情報】【最新の法改正情報】から【助成金関連情報】まで、当サイトにある全ての記事内容を閲覧することができます。
育児休業給付金の支給対象者
育児休業給付金を受給することができるのは・・・
- 雇用保険に加入している労働者
- 育休開始日(*1)の前日から「1カ月毎」に24回(2年間)さかのぼった各月=完全月(*2)の中に、賃金支払いの基礎となった「日数」が11日以上、又は「時間数」が80時間以上ある月が12か月以上ある労働者
となります。
(*1)
産前産後休業(産休)から引続き育休を取得した場合で、育休開始日の前日からさかのぼり判定した場合に支給要件を満たさない場合は、産休開始日の前日からさかのぼり判定することができます。また、育休開始日前2年間に、「疾病・負傷等やむを得ない理由」により引き続き30日以上「賃金の支払いを受けることができなかった期間」がある場合は、その期間を2年間に加算し、さかのぼった範囲内(合計4年間が上限)で判定することができます。
(*2)
賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、時間数が80時間以上あったとしても算定期間が1か月に満たない月(入社直後の月等)は完全月として数えませんのでご注意下さい。
【上記2年間の判定期間中に私傷病による休業・介護休業・産休・育休等の期間がある場合】
上記2年間の判定期間中に、「疾病・負傷等やむを得ない理由」により引き続き30日以上「賃金の支払いを受けることができなかった期間(*)」がある場合は、その期間を2年間に加算し、合計4年間までの範囲で判定することができます。
(*)「賃金の支払いを受けることができなかった期間」について
上記「賃金の支払いを受けることができなかった期間」が、育休(もしくは産休)開始日の前日からさかのぼった2年間よりも前にスタートしている場合は、その期間がスタート時点から連続している場合に限り、その全期間を2年間に加算し、合計4年間までの範囲で判定することができます。
【上記の判定期間中に転職している場合】
2年間(もしくは最長4年間)の判定期間中に転職している場合は、前職での勤務期間も通算して判定を行うことができます。
ただし・・・
- 前職でも雇用保険に加入していたこと
- 前職を離職後に基本手当等の雇用保険失業給付について受給資格を取得していないこと
- 前職を離職後、現職へ再就職するまでの間に1年以上の空白期間がないこと
が必要となります。
また、現職において育児休業給付金の初回申請(育児休業給付受給資格確認票の申請)を行う際には、前職を離職した際に発行された「雇用保険被保険者離職票-2」の写しを添付する必要があります。
前職を離職した際、上記離職票の発行を受けていない場合は、育児休業給付金の申請手続きを行う前に、前職へ発行手続きを行ってもらわなければなりませんので注意が必要です。
育児休業は取得できても、育児休業給付金の支給対象とならない労働者がいる
- 育児休業制度は「育児介護休業法」により「仕事と育児の両立支援」を目的として定められています。
- いっぽう、育児休業給付金制度は「雇用保険法」に基づき、雇用保険加入者に対して定められています。
このため、育児休業制度自体は、育児休業給付金の支給要件を満たしているか否かに関わらず適用されることとなります。
よって、法的に育児休業は取得できるものの、育児休業給付金を受給できない労働者が出てきますので注意しておかなければなりません。
育児休業給付金の支給対象外となる方
以下に該当する方は、育児休業給付金を受給することができません。
雇用保険に加入していても受給できない労働者
- 育児休業開始日(*1)の前日から「1カ月毎」に24回(2年間)さかのぼった各月=完全月(*2)の中に、賃金支払いの基礎となった「日数」が11日以上、又は「時間数」が80時間以上ある月が12か月以上ない労働者
- 退職予定の労働者
(*1)
産前産後休業(産休)から引続き育休を取得した場合で、育休開始日の前日からさかのぼり判定した場合に支給要件を満たさない場合は、産休開始日の前日からさかのぼり判定することができます。また、育休開始日前2年間に、「疾病・負傷等やむを得ない理由」により引き続き30日以上「賃金の支払いを受けることができなかった期間」がある場合は、その期間を2年間に加算し、さかのぼった範囲内(合計4年間が上限)で判定することができます。
(*2)
賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、時間数が80時間以上あったとしても算定期間が1か月に満たない場合(入社直後等)は完全月として数えませんのでご注意下さい。
雇用保険の加入対象外となっているため受給できない労働者
- 週所定労働時間が20時間未満の労働者
- 学生の労働者*(通信・夜間・定時制の学生は除く)
*卒業見込み証明があり、正式入社を前提に、一般労働者と同様に勤務している学生も除きます
- 農林水産業に従事する、常時雇用者5名未満の小規模個人事業者*の元で働き、雇用保険に加入していない労働者
*上記の個人事業者は雇用保険への加入が任意となっています
もともと育児休業の取得対象外となっている労働者
本題からは外れますが、育児介護休業法において、育児休業の取得対象外となっている労働者についても触れておきます。
育児休業給付金は、育児介護休業法に基づく育児休業を取得する労働者に対して支給することが前提となっていますので、そもそも育児介護休業法によって育休対象外とされている以下の労働者には支給されません。
- 育児介護休業法で認める理由以外で育児の為の休業を取得した労働者
- 日雇い労働者(*1)
- 期間雇用で、子が1歳6か月になる日の前日までに契約終了することが明らかな労働者(*2)
- 労使協定で育児休業取得対象外としている労働者
*1)
「日雇労働被保険者」として雇用保険に加入できる場合がありますが、育児介護休業法において育児休業の取得対象者から除外されているため受給できません。
*2)
期間雇用で、2歳まで育休延長を申請する場合は、2歳誕生日の前日までに、契約終了することが明らかな労働者は対象外となります。
会社役員は育児休業給付金を受給できない
会社役員は、原則、育児休業給付金を受給することはできません。
会社役員には雇用保険が適用されず、日頃から雇用保険料も支払っていません。
また、育児介護休業法も適用対象外となっており、そもそも育児休業制度自体、利用することができません。
よって、仮に育児のために休業したとしても育児休業給付金を受給することはできません。
ただし、例外として雇用保険に加入している使用人兼務役員については、一般の労働者と同様、育児介護休業法が適用され、育児休業給付金についても受給することができます。
育児休業給付金申請~支給のタイミング
申請は「支給単位期間」毎に行う
この「支給単位期間」とは、育児休業開始日~その翌月応当日の前日を指します。
例えば、育児休業開始日が4月10日であったならば、4月10日~5月9日が初回「支給単位期間」ということになります。
ちなみに、育児休業終了日が属する最後の支給単位期間のみは、育児休業終了日までの実日数による期間(*)となります。
(*)申請期間の中に育児休業による全日休業日が1日以上なければなりません。
(*)育児休業給付金の支給対象期間は、最長で子の1歳誕生日(延長の場合1歳6か月もしくは2歳誕生日)の前々日までとなります。
(1歳誕生日(延長の場合1歳6か月もしくは2歳誕生日)前々日よりも前に育児休業が終了する場合は、当該終了日まで支給されます)
例えば、最終回の支給単位期間初日が11月10日で、育児休業終了日(誕生日の前日でない場合)が11月27日であったならば、最終回の「支給単位期間」は11月10日~11月27日となります。
初回支給申請は、育休開始から2か月経過後に行うのが原則
育児休業給付金の申請は、休業する本人が希望する場合は「1支給単位期間」毎に行うことができますが、原則的には「2支給単位期間」毎に行います。
その後の申請スケジュールについても「2支給単位期間」毎に行っていくこととなります。
支給決定後、約1週間で給付金が入金されますが、支給決定までに時間がかかる場合もありますので、申請後に指定の銀行口座へ入金されるまでは、さらに1カ月程度かかると見ておくのが無難です。
初回申請期限は、育休開始日から4カ月を経過した月の末日
申請手続きは、原則、勤務先の会社を通じて所轄のハローワーク(もしくは電子申請により雇用保険事務センター)あてに行います。
初回給付金の支給申請期限は、育休開始日から4カ月を経過する日の属する月の末日までとなっています。
(2回目以降の申請期限は当局が指定します)
よって、支給申請を行うタイミングによっては、指定銀行口座への入金がさらに遅れることになります。
この点は、育児休業を取得するご本人に対して、事前に伝えておきたいところです。
育児休業を分割取得する場合
育児休業を2回に分割して取得する場合(*)の給付金申請についても、1回目・2回目各々につき上記同様のスケジュールで行うこととなります。
(*)やむを得ない事由により3回以上分割取得する場合も同様となります
支給額について
育休開始から180日目までの月額支給額
育児休業開始日から180日目までの月額支給額は・・・
育休(産休)開始前(*1)6か月間の賃金総額 ÷ 180日 × 30日(*2)× 67%
~支給上限額315,369円・下限額57,667円(令和6年8月1日~)
*1)
産前産後休業に引続き育児休業を取得する場合は、産前休業開始前とします。
*2)
最終回の支給月については、上記「30日」を「実日数」に置き換えて計算します。
(支給上限・下限額は日割り計算となります)
となります。
なお、上記の「育休(産休)開始前6か月間の賃金総額」とは・・・
休業開始日直前にある「賃金締切り期間」のうち、「賃金支払い基礎日数が11日以上」もしくは「賃金支払い基礎となった時間数が80時間以上」を満たす期間(=完全賃金月)のみを6か月分集めてきて合計した金額
のことを指します。
育児休業給付金の「支給要件」は、育休(あるいは産休)開始日前日から遡及した「完全月」を基準として判定するのに対し、「支給額算定」は、育休(あるいは産休)開始日直前の賃金締切日から遡及した「完全賃金月」を基準として算定が行われますので注意が必要です。
日給制賃金の場合の例外について
日給制の労働者については、上記の「育休開始前(*)6か月間の賃金総額÷180日」(賃金日額と呼びます)の部分について、「育休開始前(*)6か月間の賃金総額÷当該6か月間の賃金支払基礎日数×70%」との比較を行い、金額の大きい方を賃金日額として育児休業給付金支給額を決定する場合があります。
(*)産休に引続き育休を取得する場合は、産前休業開始前とします。
具体的には・・・
- 1週間の所定労働時間数が30時間以上
- 上記6か月間の賃金支払基礎日数が125日以下
のいずれにも該当している日給制の労働者が対象となります。
なお、「時間給×総勤務時間数(賃金締切り期間中の勤務実績)」により毎月の賃金支給額を決定している場合も「日給制」として取扱います。
令和7年4月1日以降、出生後休業支援給付金の上乗せ支給が開始される
令和7年4月1日以降は、子の出生直後の一定期間内において、両親ともに14日以上の育児休業(出生時育児休業を含む)を取得した場合、28日分までを上限に、出生後休業支援給付金として、(出生時)育児休業給付金にプラスして13%の上乗せ支給が行われます。
(配偶者が育休対象者でない場合等、特定の事情がある場合は、本人のみ14日以上の育休取得でも支給されます)
こちらの制度について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照下さい。
育休開始から181日目以降の月額支給額
育児休業開始日から181日目以降の月額支給額は・・・
育児(産休)開始前6カ月間の賃金総額 ÷ 180日 × 30日 × 50%
~支給上限額:235,350円・下限43,035円(令和6年8月1日~)
となります。
なお、「出生時育児休業(産後パパ育休)」の後に「通常の育休」を取得した場合については、両方の休業期間を通算し、初回の休業開始日から180日を経過していれば、この算式で支給額を算定することとなります。
「通常の育休」を「出生時育休」の後に取得しても180日のカウントはリセットされず、「出生時育休」の開始日を起点としてカウントしますので注意して下さい。
なお、「出生時育児休業(産後パパ育休)」「出生時育児休業給付金」については、以下の記事で詳しく解説しております。
多胎出産でも育児休業給付金は増額されない
なお、育児休業給付金は、双子以上の出産であっても給付金額が増額されることはなく、子1人を出産した場合と同額になります。
支給期間について
育児休業給付金は、最長で、子の1歳誕生日の前々日まで(*)支給されます。(育児休業期間は、最長で子の1歳誕生日前日までと定められているのに対し、給付金の最長支給期間は1日短く定められています)
(*)育児休業期間の延長が認められる場合は、上記と同様の考え方により育児休業給付金の支給期間も延長されます。
なお、子の1歳誕生日前々日より前に育児休業を終了する場合は、育休終了日までの日数分しか給付金は支給されません。
育休期間中やむをえず退職することとなった場合
育休期間中、やむをえず退職することとなった場合については・・・
育児休業開始日~その翌月応当日前日までを初回期間とし、以後1カ月毎に区切った各「支給単位期間」において、
退職日の属する「支給単位期間」の「1つ前の支給単位期間」までしか支給は行われませんので注意が必要です。
ただし、退職日が「支給単位期間」の末日である場合は、退職日を含む「支給単位期間」分についても受給することができます。
育休期間を延長した場合
子が待機児童となり、保育園等に入れない場合は、1歳6か月となる日の前日まで育児休業を延長できます。
それでも入園できない場合は、最長2歳誕生日の前日まで延長できます。
また上記の延長理由に加え、育休対象児を養育する予定であった配偶者等が死亡・けが・病気・離婚等、急遽やむを得ない理由によって育児をすることができなくなった場合についても同様に延長が認められる場合があります。
上記にともない・・・
- 育児介護休業法に基づく育児休業延長期間は、育児休業給付金も延長して受給できます。
- 支給最終日は、1歳6か月(あるいは2歳)となる日の前々日分までの支給となります。
育児休業給付金の支給調整(不支給となる場合)
育児休業給付金の支給対象となる休業期間中に、一定以上就労した場合、もしくは給与が支払われた場合には・・・
- 給付金が不支給もしくは減額支給される
こととなります。
具体的には、以下の場合に育児休業給付金の全額が不支給となります。
「育休開始日~その翌月応当日前日」までを初回期間とし、以後1カ月毎に区切った各「支給単位期間」において・・・
- 10日間かつ80時間を超えて就労した場合、または
- 休業開始時賃金月額(*)の80%以上の「給与」が支払われた場合
なお、不支給となる給与支払額の基準は、「育休給付金支給額」の80%以上ではなく「休業開始時賃金月額*」の80%以上となっておりますので、間違えないよう注意が必要です
休業開始時賃金月額とは
休業開始時賃金月額は、
- 育休(産休)開始前6か月間の賃金総額÷180日×30日
によって計算されます。
上記金額に67%(あるいは50%)を乗じた金額が、育児休業給付金の支給額となりますので・・・
- 休業開始時賃金月額とは「掛け目を乗じる前の6か月賃金平均額」
に相当します。
支給調整の対象となる給与の定義
休業開始時賃金月額の80%以上の「給与」が支払われた場合、育児休業給付金は不支給となりますが・・・
ここでいう80%以上の給与が支払われた場合の「給与」とは、以下の定義にしたがって支払われた賃金の合計額を指します。
育児休業給付金は、「育児休業開始日~その翌月応当日前日」までを初回期間とし、以後1カ月毎に区切った各「支給単位期間」毎に支給額を算定しますが、上記の対象となる「給与」とは・・・
- 支給単位期間中に支払日が到来したものであり、かつ
- 実際に育児休業した日に対してのみ支払われた給与・手当等の賃金総額(*)
のことを指します。
(*)時間外手当・精皆勤手当・通勤手当等も含めた全ての賃金総額
育児休業した日以外を一部分でも含んでいる給与の取扱い
育児休業した日以外を計算対象とした賃金を一部分でも含んでいる「給与」については、原則、その全額を支給調整の対象としないルールになっています。
ただし、上記「給与」の中から、育児休業した日のみに対して支払われた金額を明確に区別できる場合は、原則にあてはめず支給調整の対象となる場合がありますので注意が必要です。(実際の支給調整は申請先当局が決定します)
例えば、
- 休業開始日が4月15日
- 賃金締切日が月末日
- 賃金支払日が翌月10日
であれば・・・
最初の「支給単位期間」は4月15日~5月14日となり、「給与支払日」は5月10日に到来します。
5月10日に支給される「給与」は、4月1日~4月30日を計算対象としており、「育休期間」外である、4月1日~4月14日を計算対象とした賃金を含んでいます。
このため、5月10日に支給される「給与」は、4月15日~4月30日の「育休期間」を計算対象とした賃金も含め、原則的にはその全額が支給調整の対象外となります。
ただし、4月15日~4月30日の「育休期間」に対してのみ支払われた給与額を明確に区別して算定できる場合には、当該金額について支給調整の対象となる場合があります。
不支給となる場合の支給調整例
以下は、育児休業給付金が不支給となる場合の支給調整例となります。
なお、実際に支給調整が行われる際には「休業開始時賃金月額」の上限額・下限額が考慮される点に注意が必要です。
■「休業開始時賃金月額」上限額:470,700円 / 下限額:86,070円(令和6年8月1日~)
【例1】
休業開始時賃金月額が30万円で、支給単位期間中に給与25万円が支払われた場合・・・
休業開始時賃金月額30万円×80%である24万円を上回る給与が支払われておりますので、給付金の全額が不支給となります。
【例2】
休業開始時賃金月額が60万円で、支給単位期間中に給与40万円が支払われた場合・・・
休業開始時賃金月額上限額470,700円の80%である、376,560円を上回る給与が支払われておりますので、給付金の全額が不支給となります。
育休給付金の支給調整(減額支給の場合)
育児休業開始日~その翌月応当日前日までを初回期間とし、以後1カ月毎に区切った各「支給単位期間」において、「休業開始時賃金月額」の80%未満の「給与」が支払われた場合については・・・
「休業開始時賃金月額」の80%相当額から「支払われた給与額」を差し引いた金額が給付金の額となります。
育児休業給付金の支給額から支払われた給与額を差し引くわけではありませんので、間違えないよう注意が必要です。
減額支給の対象外となる場合(育休開始日から180日目まで)
ただし育児休業開始日から180日目までの間は・・・
支払われた給与額が「休業開始時賃金月額」の13%以下であれば、給付金は減額されません。
育児休業開始日から180日目までの給付金支給額は「休業開始時賃金月額」×67%となっており、支払われた給与額が「休業開始時賃金月額」×80%と67%との差である13%以内におさまっていれば、給付金の支給額(休業開始時賃金月額×67%)に影響を与えることはないためです。
減額支給の対象外となる場合(育休開始日から181日目以降)
育児休業開始日から181日目以降については・・・
支払われた給与額が「休業開始時賃金月額」の30%以下であれば、給付金は減額されません。
育児休業開始日から181日目以降の給付金支給額は「休業開始時賃金月額」×50%となりますので、支払われた給与額が「休業開始時賃金月額」×80%と50%との差である30%以内におさまっていれば、給付金の支給額(休業開始時賃金月額×50%)に影響を与えることはありません。
減額支給となる場合の支給調整例
以下は、育児休業給付金が減額支給となる場合の支給調整例となります。
なお、実際に支給調整が行われる際には「休業開始時賃金月額」の上限額・下限額が考慮される点に注意が必要です。
■「休業開始時賃金月額」上限額:470,700円 / 下限額:86,070円(令和6年8月1日~)
【例1】
休業開始時賃金月額が30万円で、支給単位期間中に給与12万円が支払われた場合・・・
休業開始時賃金月額30万円×40%である12万円が給与として支払われておりますので、休業開始時賃金月額30万円×80%である24万円と12万円との差額である、12万円が支給されます。
【例2】
休業開始時賃金月額が30万円で、休業開始日から180日目までの間にある支給単位期間中に、給与3万円が支払われた場合・・・
休業開始時賃金月額30万円×10%である3万円が給与として支払われておりますが、休業開始時賃金月額30万円×13%以下であるため、給付金は減額されず、その全額が支給されます。
【例3】
休業開始時賃金月額が30万円で、休業開始日から181日目以降にある支給単位期間中に、給与9万円が支払われた場合・・・
休業開始時賃金月額30万円×30%である9万円が給与として支払われておりますが、休業開始時賃金月額30万円×30%以下であるため、給付金は減額されず、その全額が支給されます。
【例4】
休業開始時賃金月額が60万円で、支給単位期間中に給与30万円が支払われた場合・・・
休業開始時賃金月額上限額470,700円の80%である、376,560円と30万円との差額76,560円が支給されます。
2人目の子の産休を続けて取得する場合の留意点
- 1人目の子の育児休業期間中に、2人目の子を妊娠し、新たな産前産後休業を取得する際に・・・
- 1人目の育児休業期間中に、10日間かつ80時間を超えて就労したことにより、育児休業給付金が不支給となった月があった場合
上記で不支給とされた月の就労に対し支払われた賃金額が、2人目の子の育児休業給付金支給額決定の際、休業開始前6か月間の賃金総額に含めて算定される場合があります。(算定基礎に含むか否かは、当局が決定します)
この場合、2人目の子の育児休業給付金支給額の減額要員となる可能性がありますので、留意しておく必要があります。
賞与を払っても給付金は減額されない
育児休業期間中に給与を支払うと、育児休業給付金が不支給もしくは減額される等、支給調整の対象となりますが、育児休業期間中に賞与を支払っても支給調整が行われることはありません。
育児休業給付金の申請の仕方
初回給付金の支給申請手続き
育児休業給付金は、「休業開始日から起算して1カ月毎に区切った各期間」を単位として支給申請を行います。
この期間のことを「支給単位期間」と呼びます。
初回給付金の支給申請は、育児休業開始日から2カ月経過後(2支給単位期間経過後)に行うことが原則とされており、以後も、原則「2支給単位期間」毎に申請していくこととなります。
ただし、最終回の支給単位期間についてのみは、休業終了日までの実日数ベースで申請を行います。
なお、休業取得者本人が希望する場合については・・・
- 勤務先の事業主を介さず、直接ハローワークへ支給申請を行うことや、
- 「2支給単位期間」毎ではなく「1支給単位期間」毎に申請すること
も例外として認められています。
初回給付金の申請書類
申請は、原則、勤務先の会社を通じて所轄のハローワークあてに行います。
なお、申請の際に必要となる書類は以下のとおりです。
【雇用保険被保険者 休業開始時 賃金月額証明書】
育児休業給付金の支給額算定上必要となる休業前賃金・手当(*)の支払い実績を報告するため提出します。
(*)休業開始前、直近6か月分の完全賃金月(賃金支払基礎日数11日以上の賃金締切り期間)について報告します
ハローワーク窓口で申請する場合は、賃金台帳・出勤簿(タイムカード)等の確認書類を持参します。
なお、同一の子について、既に「出生時育児休業給付金」を受給済である場合、もしくは、育児休業を分割して取得した場合で、1回目の休業にかかる「育児休業給付金」を受給済である場合については、この申請は不要です。
【育児休業給付受給資格確認票 兼 (初回)給付金支給申請書】
育児休業給付金を支給申請するにあたり、支給要件をクリアしているか?の確認と、初回の給付金を受給するために申請します。
初回「支給単位期間」中の就労実績・賃金支払い実績についてもあわせて報告します。
この申請を行う際には、母子健康手帳のコピー(*)等、育児中であることのエビデンスを添付する必要があります。
(*)保護者氏名・生年月日・居住地・電話番号・出生届出済証明欄が確認できるページを指します
通常、上記の書類2点は初回給付金申請時に提出しますが、賃金月額や受給資格確認のみを先行するため、初回給付金の申請を行う前に提出することも可能です。
この場合は、改めて「育児休業給付金支給申請書」を提出し、初回給付金の支給を申請する必要があります。
なお、同一の子について、既に「出生時育児休業給付金」を受給済である場合、もしくは、育児休業を分割して取得する場合で、1回目の休業にかかる「育児休業給付金」を受給済である場合については、再度の「賃金月額証明」および「受給資格確認」手続きは不要となります。
ただし、この場合も、初回「支給単位期間」分の申請を行う際には、「育児休業給付金支給申請書」ではなく「 育児休業給付受給資格確認票 兼(初回)給付金支給申請書 」を用いて申請を行う必要がありますので注意が必要です。
ちなみに、育児休業給付金における初回給付金の支給申請期限は、育児休業開始日から4カ月を経過する日の属する月の末日までとなります。
令和7年4月1日以降は、出生後休業支援給付金の上乗せ支給を申請できる
令和7年4月1日以降は、子の出生直後の一定期間内において、両親ともに14日以上の育児休業(出生時育児休業を含む)を取得した場合、28日分までを上限に、出生後休業支援給付金として、(出生時)育児休業給付金に13%の上乗せ支給が行われます。
(配偶者が育休対象者でない場合等、特定の事情がある場合は、本人のみ14日以上の育休取得でも支給されます)
こちらの制度を申請する場合は、上記②で解説した(初回)給付金申請書(書式は制度開始時より改定されます)を用い、一括して手続きを行うこととなります。
詳細については以下の記事をご参照下さい。
次回以降の給付金支給申請書類
【育児休業給付金支給申請書】
次回(3回目)以後の「支給単位期間」分を受給するために申請し、該当する期間中の就労実績・賃金支払い実績等をあわせて報告します。
初回支給申請を行う前に、受給資格確認の申請のみ先行した場合は、初回申請時にもこの書式を利用します。
初回支給申請を行った後、およそ2カ月間経過する毎に、2回目・3回目の順で申請を行っていきます。
(2回目以降の具体的な申請スケジュールはハローワークが指定します)
パパママ育休プラス制度を利用する場合
パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は・・・
給付金の最終回申請(子の「1歳誕生日」前々日までの期間を含む申請)を行うまでに、
- 配偶者の育児休業取得の有無と
- 配偶者の雇用保険被保険者番号(雇用保険に加入している場合のみ)
を「育児休業給付金支給申請書」に設けられている所定欄(*)へ記入する必要があります。
(*)初回申請時に「育児休業給付受給資格確認票 兼(初回)給付金支給申請書」の所定欄へ記入し申請することもできます
パパママ育休プラス制度を利用することにより、最長で、子が1歳2か月に到達する日(*)まで、育児休業期間を延長することができます。
(*)1歳2か月の誕生日に応答する日の前日を指します
それに伴い、育児休業給付金を受給できる最長期間も、子が1歳2か月に到達する日の前日まで延長することができます。
なお、申請の際には、以下のエビデンスを添付する必要があります。
- 世帯全体について記載された住民票の写し
(事実婚の場合は、住民票に代えて民生委員の証明書が必要となります)
~配偶者と同居していることを証明するために提出します。 - 配偶者の勤務先が発行した「育児休業取扱通知書(*)」の写し等、配偶者が育児休業を取得していることが確認できる書面(無い場合は配偶者が作成した疎明書が必要となります)
~配偶者が育児休業を取得していることを証明するために提出します。
ただし、②の「育児休業取扱通知書(*)」写し等のエビデンスについては、申請書の所定欄に、配偶者の雇用保険被保険者番号を記載した場合で、かつ、ハローワークが配偶者の育児休業給付金受給状況を確認できる場合は、提出しなくても構いません。
(*)「育児休業取扱通知書」の詳細については 育児休業取扱通知書の作成・通知 をご参照下さい。
育児休業を分割取得する場合の申請方法
育児休業を分割取得する場合は、それぞれの休業期間に対し、個別に上記スケジュールにしたがって申請を行うこととなります。
なお、初回休業時の給付金申請(*1)において、 「雇用保険被保険者 休業開始時 賃金月額証明書」ならびに「育児休業給付受給資格確認票」を提出済である場合は、2回目休業時(*2)の給付金申請の際に再提出する必要はありません。
(*1)出生時育児休業給付金の申請も含みます
(*2)やむを得ない事由により3回目の休業をする場合も含みます
ただし、2回目(以降)の休業であっても、その初回給付金申請時には「育児休業給付受給資格確認票 兼 (初回)給付金支給申請書」の書式を用いて申請しなければなりませんので注意が必要です。 (受給資格確認の手続きは行われません)
育休期間中の従業員を転籍させる場合の給付金申請方法
勤務先の会社が買収され、買収先企業が雇用を引継ぐ場合などには、育児休業期間中の従業員を転籍させる必要が生じます。
このような場合、もともと育児休業中であった旧勤務先は雇用保険被保険者資格を喪失させ、買収先企業が新たに雇用保険被保険者として資格を取得させなければなりません。
買収先企業が育児休業中の従業員の雇用を引継ぐ時には、そのまま育児休業を取得させ続けるのが通例ですが、このような場合の育児休業給付金支給申請手続は以下の通りとなります。
【注意点】
①必ず、旧勤務先の退職日と新勤務先入社日の間に空白が生じないようにしなければなりません。
②前勤務先・新勤務先の両方で、それぞれを管轄するハローワークあてに手続きが必要となります。
~前勤務先と新勤務先との間で、交互に管轄ハローワークあて申請を行う必要がありますので、相互に連絡を取り合い、もれがないように手続きを進める必要があります
【手続きの順序】
①前勤務先が雇用保険資格喪失届を提出
↓
②新勤務先が雇用保険資格取得届を提出
↓
③前勤務先が雇用保険資格喪失日までの「育児休業給付金支給申請書」を提出
(必ず②の手続きが終わってから提出しなければなりません)
↓
④新勤務先が「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を提出
【新勤務先の申請手続き】
■新勤務先では「休業開始時賃金月額証明書」の提出は不要です。
■入社日(雇用保険被保険者資格取得日)が「育児休業開始」年月日となります。
■支給申請書を提出する際、「育児休業申出書」「雇用契約書」等、転籍後も継続して育児休業を取得していることが確認できる書類を添付しなければなりません。
■「支給単位期間その1」は「入社日」から「入社1カ月後応当日の前日」までとなります
■「支給単位期間その2」は「入社1カ月後応当日」から「入社2か月後応当日の前日」ま
でとなります
当事務所では、小規模企業でも産休・育休手続きを円滑に進められるよう・・・
産休・育休手続ナビゲーション+申請手続代行サービスを
顧問契約不要・安心の一括スポット料金でご提供しております。
メールのみで・・・
- お申込み(別途 書面の郵送が必要となります)
- 最新の産休・育休制度情報収集
- 産休・育休、各種事務手続のアウトソーシング
まで、一筆書きで完了させることができる画期的なサービス内容となっております。
あわせて・・・
- 育休関連助成金の申請サポート【事前手数料なし / 完全成果報酬制】
- 助成金サポートのみ お申込みもOK
にも対応しております。(東京しごと財団 働くパパママ育業応援奨励金 の併給申請サポートも可能です)
完全オンライン対応で、就業規則等改定~助成金(奨励金)申請代行まで個別にサポート致します。
- 産休・育休取得実績が乏しい小規模企業のご担当者様
- ご多忙につき、「情報収集の時間確保」が難しいご担当者様
- 業務中断せず、自分のペースで支援を受けたいご担当者様
から大変ご好評いただいております。
【全国47都道府県対応】
メールで気軽に支援が受けられる!
当サービスをご利用いただくと、以下1~7の全てを、一筆書きで完了させることができます。
- 産休・育休申出者への相談対応に必要となる最新の制度情報収集
- 休業申出書・育休取扱通知書等、各種必要書面の準備
- 切迫早産・切迫流産等発生時の傷病手当金(*)、帝王切開時の高額療養費限度額適用認定(*)申請
- 出産手当金(*)・育休給付金・社会保険料免除等、産休・育休に必要な全ての申請(手続代行)
- 社会保険料引き落しの停止や地方税徴収方法変更等、給与支払事務の変更手続
- 職場復帰後の「休業終了時 社会保険料特例改定」(手続き代行)
- 「厚生年金保険料 養育期間特例適用」申請(申請書作成のみサポート)
(*)電子申請できない書類は書面作成のみサポート致します。

CLASSY. 2024年2月号に掲載されました
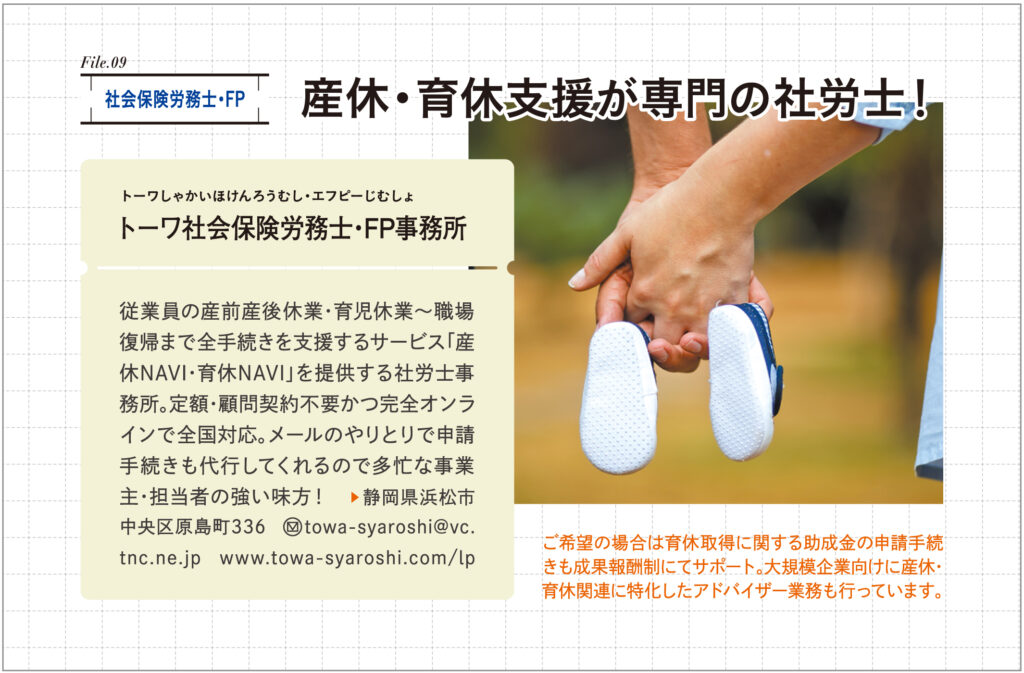
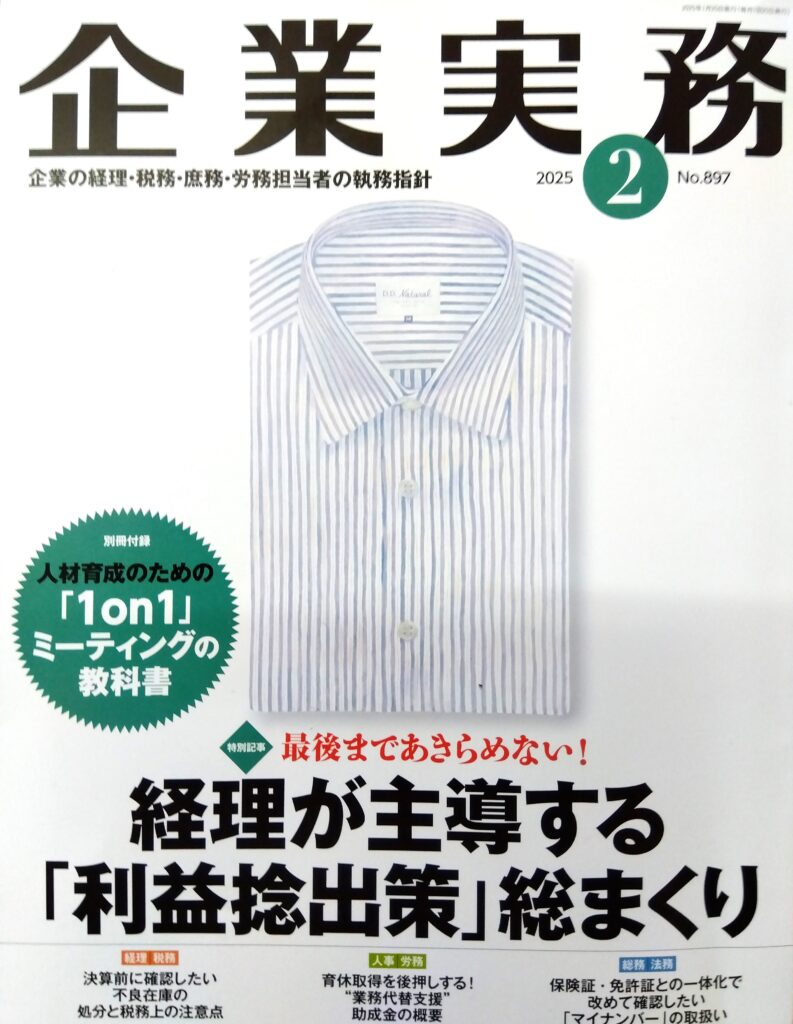
企業実務2025年2月号に寄稿させていただきました
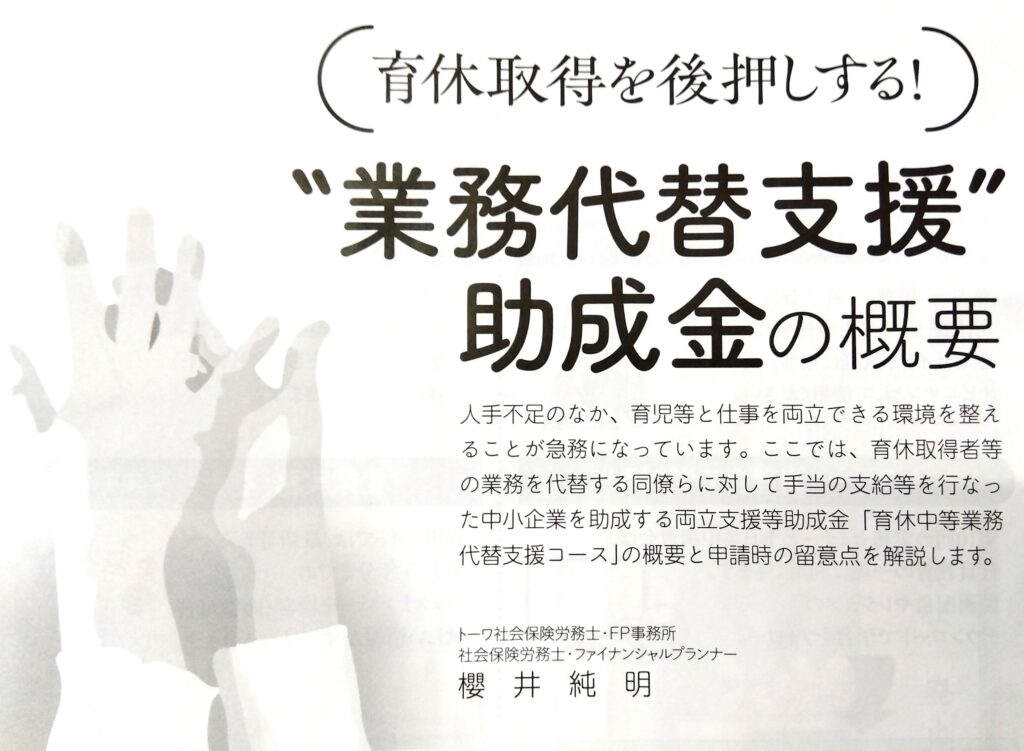
【両立支援等助成金活用のご案内】
従業員の育休取得を推進する中小企業に対しては、非常に手厚い助成金制度が設けられています!
育休関連の助成金制度について知りたい方は、以下のサイトもご参照下さい。
欠員補充コストでお悩みの事業主様には、是非とも知っておいていただきたい内容となっています。
産休・育休関連情報 総合ページへのリンクはこちら!
以下のページからアクセスすれば、産休・育休関連の【各種制度・手続き情報】【最新の法改正情報】から【助成金関連情報】まで、当サイトにある全ての記事内容を閲覧することができます。


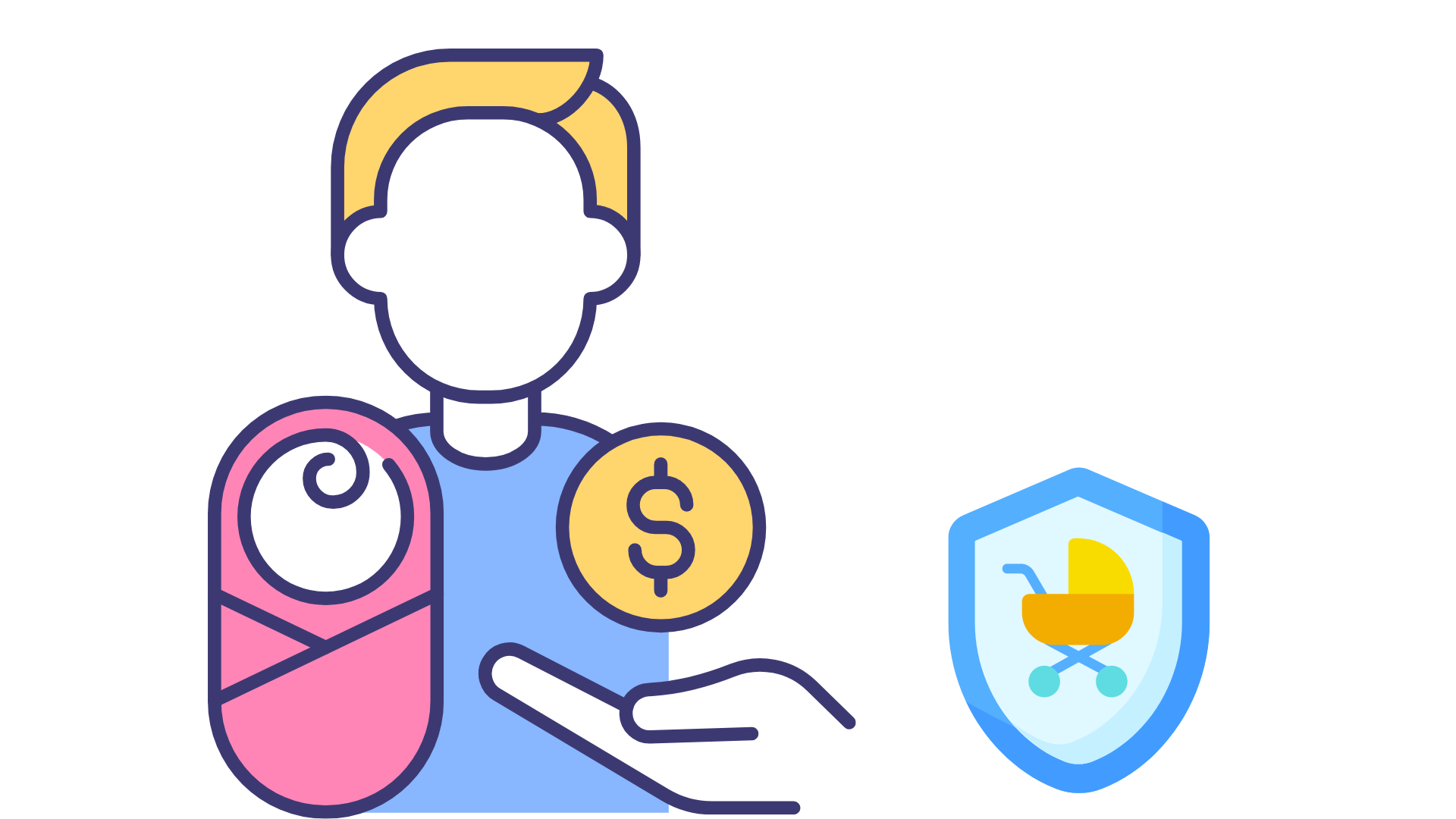



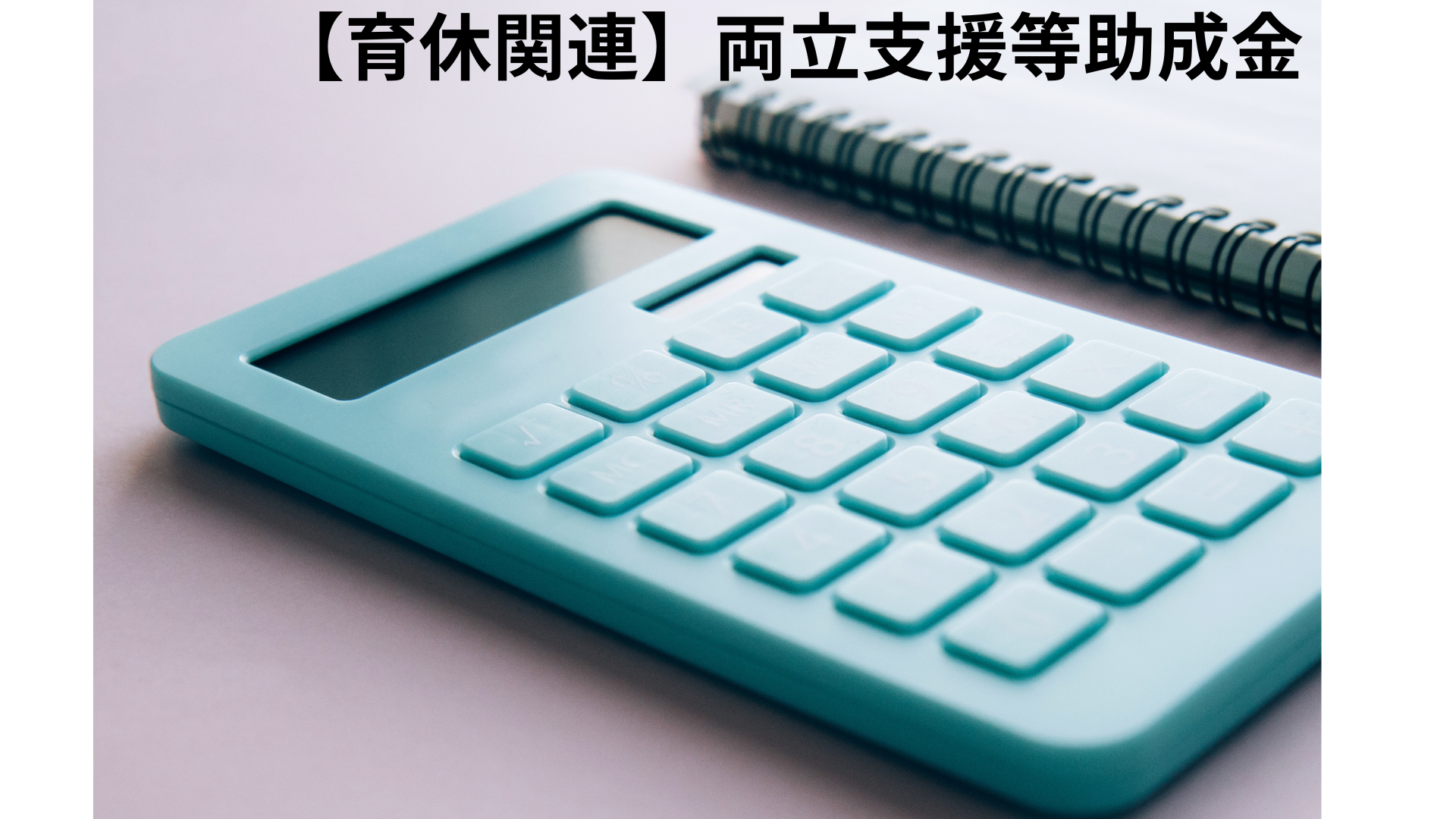


②.png)